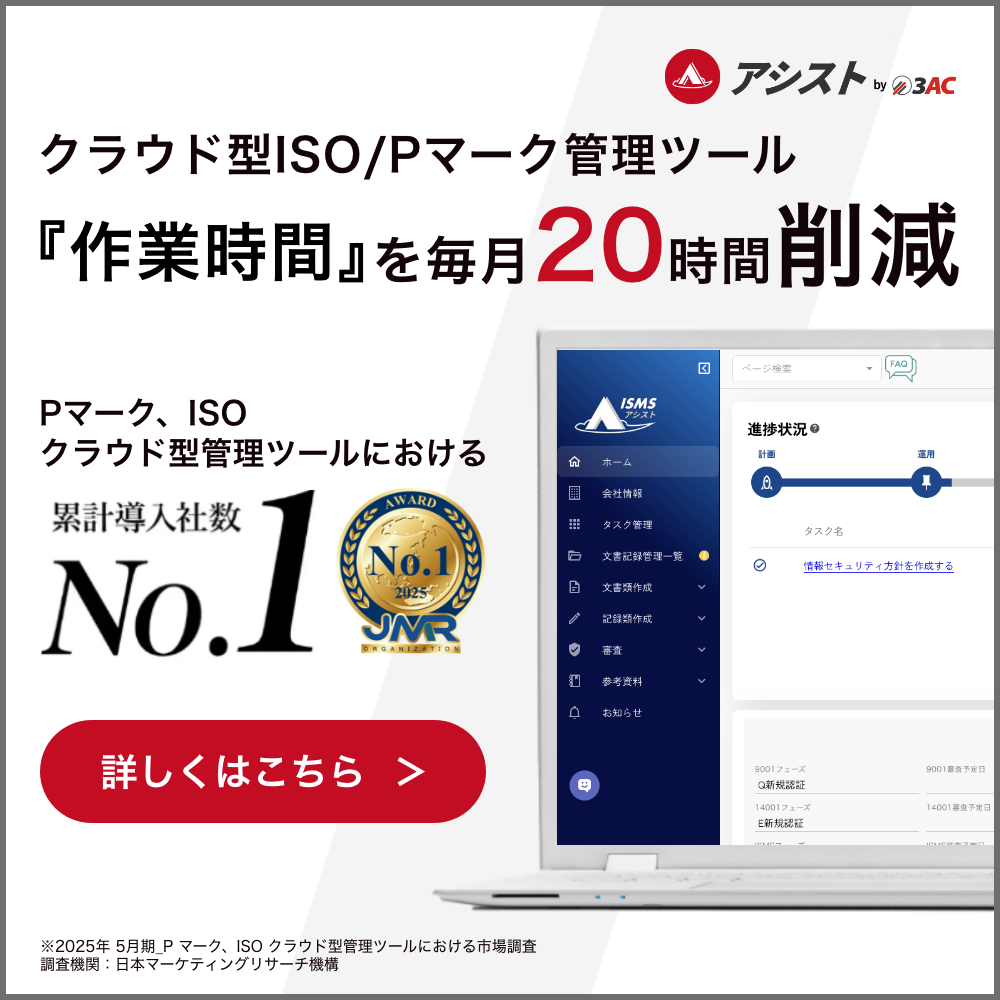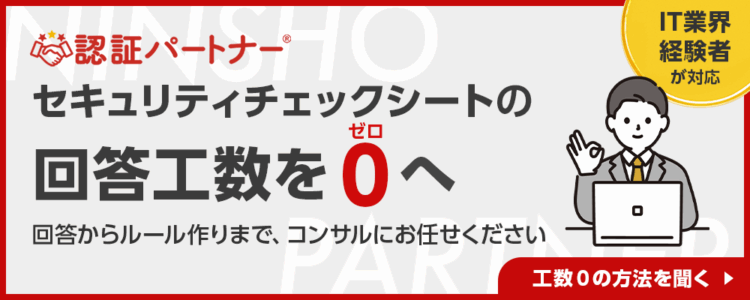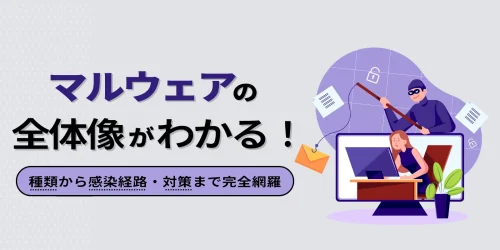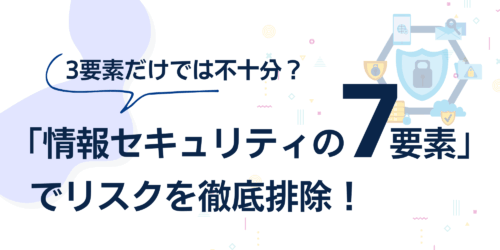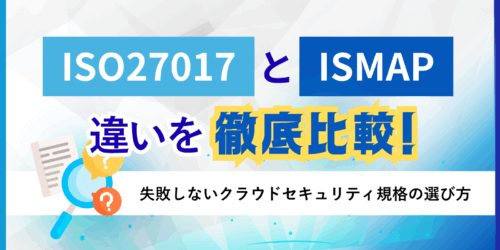2025年5月8日
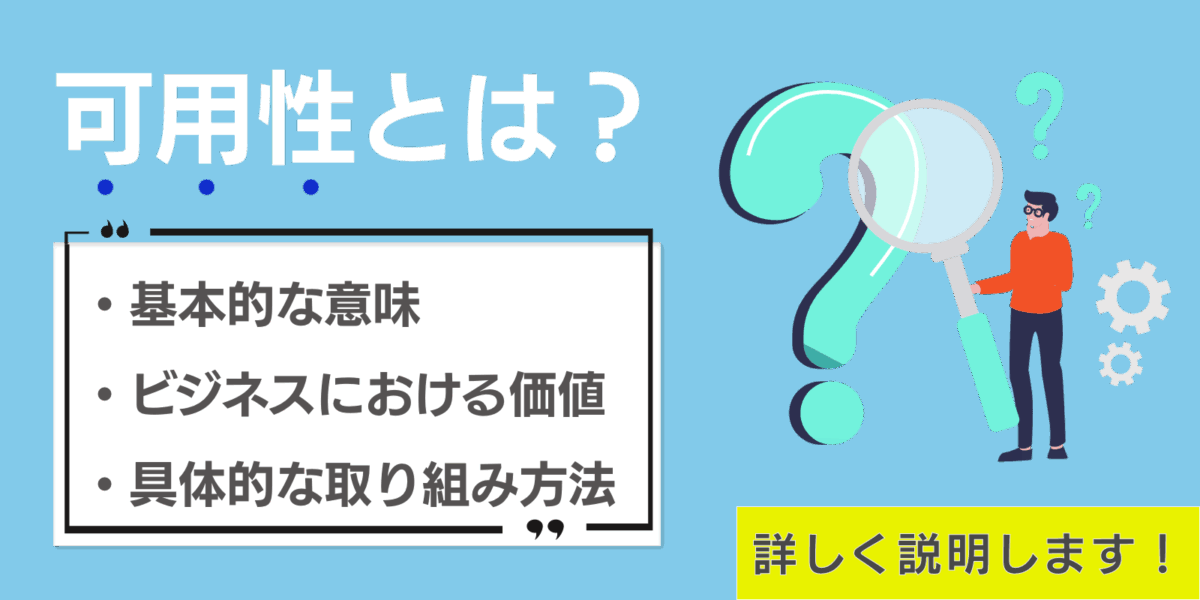
目次
Close
「可用性って何?」「どうすればシステムが安定して使えるの?」
そんな悩みを抱えていませんか?
結論からお伝えすると、可用性とは「いつでも使える状態を保つこと」であり、そのためには仕組みづくりと日々の管理が大切です。このことは、経済産業省の「情報セキュリティ管理基準」にも明記されています。
なぜなら、どんなにすごいシステムでも、使いたいときに使えなければ意味がないからです。
可用性が高いということは、仕事やサービスが止まらずにスムーズに進むということ。これはビジネスにとってとても価値のあることです。
この記事を読み終わるころには、なぜ「可用性」が大事なのか、どうすれば高められるのかがわかるようになります。
1.可用性とは「使いたいときに使える状態」のこと

「可用性(かようせい)」とは、システムやサービスが、使いたいときにきちんと使える状態にあることを意味します。
たとえば、スマートフォンで地図アプリを開こうと思ったとき、アプリがうまく動かず開けなかったら困りますよね。
必要なときにサービスが使えないと、利用する人にとって不便を感じてしまいます。
反対に、どんなときでも止まらずに使えるアプリやシステムは、「可用性が高い」と言えます。会社で使っているメールや予約システム、オンラインショップなど、どれも「止まらずに動く」ことが実はとても大切なのです。
つまり、可用性とは「いつでも正しく使える」ことを保証する仕組みであり、便利さや信頼を守るために欠かせない考え方なのです。
(1)補足:信頼性と保守性の違い
「可用性」と合わせてよく出てくる言葉に「信頼性」や「保守性」がありますが、それぞれの意味は少しずつ異なります。
まず、信頼性とは「長い時間にわたって正しく動き続ける力」のことを指します。一度も止まらず、エラーもなく、安定して働き続けることが求められます。
一方で、保守性とは「トラブルが起きたときに、すばやく直せるかどうか」や「手入れや更新がしやすいかどうか」といった面を表します。
たとえば、ある機械が10年間一度も壊れなければ、それは信頼性が高いと言えます。一方で、壊れてもすぐに直せるよう設計されていれば、保守性が高いと言えるのです。
信頼性は「壊れにくさ」、保守性は「直しやすさ」と考えると、イメージしやすくなります。
どちらも、システムやサービスを安定して使うためには欠かせない大切な考え方です。可用性とあわせて理解しておくと、より深く全体像がつかめるようになります。
2.可用性を高めることが重要な理由
可用性が低いために、システムやサービスが止まってしまうと、ただ「使えなくて困る」というだけでは済みません。大きな損失が出るおそれがあるため、とくに注意が必要です。
たとえば、オンラインショップが数時間の間、使えなくなったとしましょう。その間に買おうとしていた人は、別の店に流れてしまうかもしれません。すると、売上が減るだけでなく、「このショップは接続が不安定」と思われ、次から来てもらえなくなることもあります。
具体的には、シャープが2020年に自社製マスクのオンライン販売を開始した際、予想を大きく超えるアクセスが集中したことで、ECサイトがダウンし、購入希望者がサイトに接続できない状態が続きました。
このトラブルは、単に「買えなかった」という機会損失にとどまらず、SNSなどで「繋がらない」「不親切」といった不満の声が広がるなど、ブランドイメージにも影響を与えました。
参考:日経クロステック「新型コロナ対策のシャープ製マスク、販売サイトに殺到でアクセス不能に」
つまり、可用性が低い状態は、目に見える金銭的な損失だけでなく、信頼や機会の損失も生むのです。だからこそ、いつでも使える状態=高い可用性を保つことが、とても大切なのです。
3.可用性を高めるための3つの取り組み
可用性を高めるためには、以下のようなポイントがあります。
- 情報セキュリティに関する責任者を明確にする
- ハードウェアを冗長化させる
- 定期的な障害対応訓練を実施する
技術的な対策に加えて体制や運用面の整備も重要です。現場任せにせず組織的に対応できる取り組みについて、順番に解説していきます。
(1)情報セキュリティに関する責任者を明確にする
可用性をしっかりと守るためには、誰がその責任を負うのかを明確にしておくことが重要です。
なぜなら、誰が対応すべきかがはっきりしていないと、トラブル発生時に復旧が遅れてしまい、可用性が損なわれる可能性があるからです。
たとえば、システムが停止した際に、「復旧の指示は誰が出すのか」「緊急時はどこに連絡すればよいのか」が決まっていなければ、社内で混乱が生じ、対応が後手に回ってしまうことも少なくありません。
その結果、サービスが長時間利用できず、業務や顧客対応にも支障、場合によっては損害が出る恐れがあります。
つまり、可用性に関する情報セキュリティの責任者を事前に決めておくことは、日常の管理だけでなく、緊急時の迅速な対応にもつながるのです。
(2)ハードウェアを冗長化させる
可用性を高めるためには、ハードウェアの冗長化が欠かせません。
冗長化とは、サーバーやストレージなどのシステム構成要素を二重化または多重化し、万が一の故障時にもサービスを継続できるようにする仕組みです。
たとえば、サーバーを2台以上用意しておけば、一方に障害が発生しても、もう一方が自動的に処理を引き継ぎます。
とくに、24時間稼働が求められる業務や、ユーザーへの影響が大きいサービスにおいては、冗長化の有無がサービスの信頼性を左右します。
このようにハードウェアの冗長化は、障害時の被害を最小限にとどめ、サービスを継続するための重要な取り組みといえるでしょう。
(3)定期的な障害対応訓練を実施する
可用性を保つためには、定期的に障害対応の訓練を行うことが大切です。
なぜなら、どれだけ設備が整っていても、実際にトラブルが起きたときにすぐに動けなければ、復旧が遅れてしまい、大きな被害につながるからです。
たとえば、サーバーが突然止まってしまったとき、誰がどのように対応するかが決まっていないと、現場は混乱し、対応が後手に回ってしまいます。
一方で、あらかじめ「誰が」「何を」「どうするか」を決めておき、定期的にシミュレーションを行っていれば、緊急時にも落ち着いて動けるようになります。
また、訓練を通じて手順の見直しや改善点も見つかるため、実際の対応力を高めることにもつながります。
NTTデータでは、社内情報システムのトラブル発生を想定した訓練を実施し、以下のような成果を上げています。
- 初動対応の迅速化:トラブル発生時の初動対応を迅速に行い、影響を最小限に抑える。
- コミュニケーションパスの整備:関係者間の情報共有手段を整備し、スムーズな連携を実現する。
- 課題の顕在化と改善:訓練を通じて課題を洗い出し、対応策を整理する。 
参考:DATA INSIGHT「大規模トラブル発生に備えた環境整備と対応訓練」
このような取り組みをしておくことで、実際にトラブルが起きたときでも、すばやく、正しく対応できるようになります。
トラブルが起きた際の混乱を防ぎ、サービスを早く復旧させるためには、事前の準備と繰り返しの訓練がとても重要です。
4.可用性を高めるうえで注意すべきこと3選
「可用性を高めれば、すべての問題が解決できる。」
そう思われがちですが、実はそうではありません。可用性を高めるときに注意すべきポイントは、大きく3つあります。
- 可用性とパフォーマンスは別もの
- 可用性とコストのバランスが大切
- 可用性が高すぎることで保守性が下がることも
それぞれについて詳しく見てみましょう。
(1)可用性とパフォーマンスは別もの
可用性が高くても、システムやサービスの使いやすさ(パフォーマンス)が高いとは限りません。
なぜなら、「止まらずに動いていること」と「速く快適に動くこと」はまったく別の指標だからです。
どれだけサービスが安定していても、表示が遅かったり、反応が悪かったりすればユーザーにとっては「使いにくい」と感じてしまいます。
たとえば、ある予約サイトがいつでもアクセスできる状態にあっても、ページを開くのに10秒以上かかってしまうと、利用者は不満を持つでしょう。
Googleの調査によると、ページの読み込み時間が1秒から3秒に増加すると、直帰率(ユーザーが最初のページだけを見て離れる割合)が32%増加します。さらに、5秒になると90%、6秒で106%、10秒で123%増加することが報告されています。
このように可用性は「いつでも使えるかどうか」、パフォーマンスは「どれだけ快適に使えるか」を表しており、どちらか一方だけが良くても、ユーザー体験は十分とは言えません。
両方のバランスをとることが、良いシステムやサービスの提供には欠かせないのです。
(2)可用性とコストのバランスが大切
可用性を高めることは重要ですが、コストとのバランスを取ることが何より大切です。
なぜなら、システムやサービスの可用性を上げようとすると、その分だけお金や人手、設備などの資源が必要になるからです。
限られた予算の中で運用するためには、「どの程度の可用性が必要か」を見きわめる力が求められます。
たとえば、小さな会社のホームページであれば、多少アクセスできない時間があっても大きな問題にはなりにくいでしょう。
しかし、ネットショップのように、サービス停止がそのまま売上の減少につながる場合は、できるだけ止まらないような仕組みが必要です。このとき、すべての部分で100%の可用性を目指すと、コストがかかりすぎて現実的ではありません。
そのため、「重要な部分だけ高い可用性を保ち、それ以外は適切な水準に抑える」という考え方が求められます。
ただ可用性を上げるだけではなく、コストとのバランスを考えて計画を立てることが、 無理のない運用とサービスの安定につながります。
(3)可用性が高すぎることで保守性が下がることも
可用性を高めすぎると、かえって保守性(直しやすさや手入れのしやすさ)が下がってしまうことがあります。
その理由は、システムを止めないようにするあまり構成が複雑になりすぎたり、更新や修理のタイミングが限られてしまったりするためです。
たとえば、24時間365日動き続けるサービスを作るために、複数の予備機を用意し、データを二重、三重に保存する仕組みを作ったとします。
すると、一部を更新したくても他の部分との連動を考える必要が出てきて、ちょっとした修正にも多くの手間がかかるようになります。
また、メンテナンスのために止めることができず、不具合の発見や改善が後回しになることもあるでしょう。
このように、「絶対に止めない」ことばかりに目を向けすぎると、保守作業がしにくくなり、かえってトラブルを長引かせてしまう可能性もあるのです。
可用性だけに目を向けるのではなく、保守のしやすさとのバランスを考えた設計が大切です。
5.まとめ
今回は、可用性の基本的な意味から、その重要性、そして注意すべきポイントまでをわかりやすく解説しました。
可用性とは、「サービスやシステムがいつでも使える状態を保つこと」です。
クラウドを使う場面が増えている今、可用性はビジネスの信頼や満足度を支える大切な考え方になっています。
ただし、可用性を高めるには、パフォーマンス・コスト・保守性とのバランスも忘れてはいけません。止まらない仕組みを目指しながらも、無理のない計画や設計が必要です。
「自社のシステムは十分な可用性を保てているのだろうか?」
「もしトラブルが起きたら、すぐに対応できる体制になっているだろうか?」
そんな不安をお持ちの方は、認証パートナーに一度ご相談ください。
専門のスタッフが無料相談を通じて、今の課題や対策についてわかりやすくアドバイスいたします。
将来のトラブルを未然に防ぐためにも、まずはお気軽にご相談ください。
ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!
認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。
経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。
▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間
- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間
- 審査資料の準備:20時間→0.5時間
認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。
ISO・Pマーク(プライバシーマーク)の認証・更新も安心
認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!
信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!
一目でわかる
認証パートナーのサービスご説明資料
8,000社以上の支援実績に裏付けされた、
当社サービスの概要を紹介しております。
資料の内容
- ・一目でわかる『費用』
- ・一目でわかる『取得スケジュール』
- ・一目でわかる『サポート内容』
ISMS(ISO27001)認証パートナー
サービスのご案内
認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。
お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。
-
Pマーク
個人情報保護マネジメントシステム
高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。
認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -
ISO9001
品質マネジメントシステム
品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。
認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -
ISMS・ISO27001
情報セキュリティマネジメントシステム
情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。
認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -
ISO14001
環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。
認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -
ISO27017など各種対応規格
ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。
ISO27017など各種対応規格ページへ -
複数規格の同時取得
ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください
複数規格の同時取得ページへ
- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.