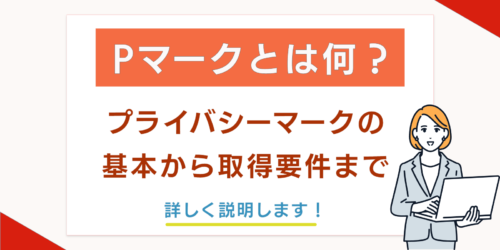Pマーク管理をクラウドツールで効率化する方法
2025年5月22日

「Pマークを取ったけど、運用が大変すぎる…」
「社内の負担が大きくて、更新を続けるか迷っている」
結論からお伝えすると、クラウド型のPマーク管理ツールを使えば、手間もコストもおさえて、運用をもっと楽にすることができます。
なぜなら、クラウドサービスを使うことで、書類や記録の管理を一か所にまとめられるだけでなく、いつでもどこからでもアクセスできるようになり、業務のムダを減らせるからです。
さらに、専門知識がなくても使えるツールを選べば、導入のハードルも下げることができます。
この記事では、Pマーク運用でよくあるやめてしまう理由と、それを解決するクラウドサービスのメリット、そしてツール選びのポイントを、わかりやすくご紹介しています。
読み終わる頃には、「これなら自社でも続けられそう」という前向きな気持ちになれるはずです。
Pマーク運用に悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
1.プライバシーマークとは?重要性を再確認
まず最初に、プライバシーマーク(通称Pマーク)の基本的な考え方とメリットについてご紹介していきます。
(1)Pマークの基本的な概要
Pマークとは、個人情報を正しく取り扱う体制が整っている企業に対して与えられる認証のことです。審査や認証は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)などの第三者機関によって行われます。
Pマークを取得することにより、「この会社は個人情報を大切に扱っている」と社外から信頼を得やすくなります。とくに、顧客の情報を日常的に扱う業種では、その信頼が新しい取引や受注につながることも少なくありません。
Pマークを取得するには、必要な書類を整えるだけでなく、日々の運用記録を残したり、社員に対して個人情報保護の研修を行ったりすることも求められます。そのため、取得後も継続的な取り組みが重要になります。
(2)Pマーク取得の4つのメリット
Pマークを取得することで得られるメリットは以下のとおりです。
- 顧客からの信頼を得やすくなる
- 取引先との信頼関係を築ける
- 社内の意識が高まる
- リスクを事前に防げる
順番に見ていきましょう。
1.顧客からの信頼を得やすくなる
Pマークを取得することで、顧客からの信頼を得やすくなります。
なぜなら、Pマークは「個人情報を適切に管理している」と第三者機関から認められた証であり、企業としての信頼性を目に見えるかたちで示せるからです。
たとえば、はじめて利用するサイトで商品を購入したり、サービスに申し込んだりする際、自分の個人情報がどう扱われるのかを気にする場合もあります。そのときに、企業のWebサイトや書類にPマークが表示されていると、「この会社はしっかり管理してくれそう」と安心してもらいやすくなります。
つまり、Pマークの取得は、情報の安全性に対する企業の姿勢を伝える手段になるのです。
2.取引先との信頼関係を築ける
Pマークを取得すれば、取引先との信頼関係を築きやすくなります。
なぜなら、個人情報の取り扱いについて、一定の管理基準を満たしていることを第三者機関から認められているため、安心して業務を任せられるという評価をされやすくなるからです。
たとえば、官公庁や大手企業などでは、業務委託先にPマークの取得を求めるケースがあります。情報を外部に預ける以上、万が一の事故が起きないよう、信頼できるパートナーであることが取引条件となっているのです。
実際に、Pマークの有無が入札や契約の可否に影響する場面も見られます。
Pマークの取得は、取引先からの信頼を得るだけでなく、新しい取引の機会にもつながります。
3.社内の意識が高まる
社内の情報保護に対する意識が高まることもPマーク取得のメリットといえます。
なぜなら、認証を受けるためには、ルールを整えるだけでなく、実際の業務でそのルールを守る体制づくりが求められるため、その過程で、従業員一人ひとりが「自分ごと」として意識するようになるからです。
たとえば、取得に向けた準備として定期的な研修を実施したり、社内マニュアルを整備したりすることで、情報管理に対する知識や判断力が会社全体で高まっていきます。
このように、Pマーク取得の取り組みは、単なる認証の取得だけではなく、社内全体の意識を変えるきっかけにもなるのです。
4.リスクを事前に防げる
Pマークの取得は、個人情報に関するリスクを事前に防ぐことにもつながります。
Pマークの取得には、社内の情報の扱い方を見直し、リスクの有無を丁寧に洗い出す必要があるからです。
たとえば、個人情報が複数の場所にバラバラに保存されていたり、アクセスできる社員が必要以上に多かったりすると、情報漏えいにつながる可能性が高まります。Pマーク取得のプロセスでは、こうしたリスクを一つずつ整理し、必要な対策を行っていきます。
つまり、Pマーク取得の取り組みは、見えないリスクに気づき、未然に防ぐことができるようになるのです。
2.Pマークの運用をやめてしまう理由TOP3

Pマークを取得したはいいものの運用面が負担になってしまうケースも少なくありません。運用をやめてしまう大きな理由は以下の3つです。
- 運用負担の大きさ
- 維持コストの高さ
- 不要なルールが増える
これらの理由を事前に把握しておくことで、運用の労力を最大限に減らすこともできます。ひとつずつ見ていきましょう。
理由① 運用負担の大きさ
Pマークをやめてしまう理由のひとつは、「運用負担が大きすぎる」と感じる企業が多いことです。
Pマークを取得した後も、ルールを新しく作ったり、記録をきちんと残したりしなければいけません。
今まで使っていた書類などが使えないことも多く、すべて一から作り直す必要があります。
とくに人数が少ない会社では、普段の業務に加えてPマークの作業もこなすことになるため、とても大きな負担になります。
業務量が増えた結果、「もう続けるのはむずかしい」と感じてしまうのです。
理由② 維持コストの高さ
Pマークの運用をやめてしまう理由として多いのが、「維持するためのコストが高い」ということです。
Pマークは、取得後も2年に1回の審査があり、その度に費用がかかります。さらに、社内で準備や対応をするための時間や人手も必要になるので、その分の人件費もかかってしまいます。
たとえば、最初にPマークを取るときには申請料や審査費用がかかります。そして更新のときにも、会社の大きさに応じて、また別の費用が発生します。
もし社内に詳しい人がいない場合は、外部の専門家にサポートをお願いすることになり、その分のコンサル料も必要です。
結果として、Pマークの維持に毎年数十万円以上かかることあるため、「ここまでお金と時間を使う価値があるのか?」と感じて、更新をやめる会社も出てきています。
理由③ 不要なルールが増える
「不要なルールが増えすぎてしまう」というデメリットもあります。
たとえば、審査を受けたときに、「ここは直したほうがよいです」と指摘されることがあります。さらに、「こういうルールも入れたほうが安心です」といったアドバイスをもらうこともあるでしょう。
これらは必ずしも間違いではありませんが、すべてをそのまま取り入れると、業務の効率が下がってしまうことがあります。
ルールが増えすぎると、ルールを守ることが目的になってしまい、本来の情報保護という目的からズレてしまうこともあります。これらがストレスとなり、Pマークの運用を断念してしまう会社もあるのです。
3.Pマークの管理にクラウドサービスを導入するとどうなる?
取得だけでなく、運用面においても会社への負担が懸念されますが、それらの管理をクラウドサービスに任せるという選択肢もあります。
ここからは、Pマークのクラウドサービスを導入するメリットについてご紹介していきます。
(1)クラウドサービスとは?
クラウドサービスとは、インターネットを使って、必要なソフトやデータを利用できるサービスのことです。
たとえば、会社の文書をクラウドに保存すれば、どのパソコンからでも中身を見ることができます。
また、離れた場所にいる人同士が同じ文書を開いて、一緒に編集したり、意見をやりとりしたりすることも可能です。
さらに、セキュリティの対策が進んでおり、クラウドサービスの中には個人情報や大切な社内情報を安心して管理できるものも増えています。
クラウドサービスは、場所や時間にしばられずに仕事を進めることができるので、多くの企業で利用されています。
(2)クラウドサービスを導入する3つのメリット
Pマークの管理にクラウドサービスを利用するメリットは以下のとおりです。
- 情報の一元管理とアクセス性の向上
- コストの削減
- セキュリティの強化
順番に解説していきます。
1.情報の一元管理とアクセス性の向上
クラウドサービスを導入することで、社内の情報を一か所にまとめて管理できるようになります。
クラウドを使えば、必要な文書やデータを一つの場所にまとめておけるため、誰が見ても内容が統一されており、無駄な作業やトラブルを減らすことができます。
さらに、インターネットが使える環境であれば、オフィスの外からでもすぐにアクセスが可能です。
出張中や在宅勤務の際にも、資料を確認したり、入力作業を行ったりできるため、業務のスピードも高まります。
このように、クラウドサービスを導入することで、情報を一か所に集約し、必要なときにすぐ取り出せる環境を整えることができます。
2.コストの削減
運用にかかるコストを抑えることもできます。
クラウドサービスは多くの場合、月額または年額の利用料のみで使うことができます。
機器の購入や保守にかかる費用が不要になるため、初期投資をおさえることが可能です。
また、アップデートや障害対応もサービス提供側が行うため、社内の負担を減らすことにもつながります。
とくにコスト面を意識したい企業にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
3.セキュリティの強化
クラウドサービスを使うことで、大切な情報を安全に守れるようになります。
最近のクラウドサービスは、セキュリティ対策がとても進んでおり、自分たちだけで情報を守るよりも、安心できる環境が整っています。
たとえば、データを見られないように暗号化したり、操作の記録を残したり、見る人を限定する機能が備わっています。
もし、社員のパソコンが壊れたり、外出先でノートパソコンをなくしたりしても、クラウドに保存していればデータは消えません。
また、見ていい人だけがアクセスできるように設定できるので、情報の漏えいを防ぐこともできます。さらに、クラウドは常に最新の状態に保たれており、新しいウイルスや攻撃にもすばやく対応できます。
自社だけで同じような対策を行うには、大きな費用と時間がかかるため、外部の信頼できるサービスを活用することは、とても効率的です。
4.クラウド型Pマーク管理ツールを選ぶポイント2点
最後に、クラウド型のPマーク管理ツールを選ぶ際のポイントについてご紹介します。
管理ツールの導入を検討されている方は、ぜひ、ご一読ください。
(1)必要な機能と特徴
クラウド型のPマーク管理ツールを選ぶときは、「何ができるか」と「どこが使いやすいか」をしっかり見ておくことが大切です。
まず注目したいのは、必要な機能がそろっているかどうかです。
たとえば、社内で使うルールや記録をまとめて管理できる機能、社員の教育記録を残せる機能、台帳を自動でつくる機能などがあります。
また、誰でも迷わず使えるような、わかりやすい画面や操作方法もポイントになります。
とくに担当者がITに詳しくない場合は、マニュアルを見なくても操作できるくらいの使いやすさが必要です。
このように、Pマークに必要な作業をまとめて支えてくれる機能があり、かつ毎日の業務に負担をかけないシンプルな操作ができるツールを選ぶことが、失敗しないためのポイントです。
(2)コストと導入のしやすさ
「費用」と「使いはじめやすさ」も重要です。
まず、費用については「初期費用がかからないか」「毎月どれくらいの金額で使えるか」を確認しましょう。
たとえば、クラウド型ISOツール「Pマークアシスト」のようなツールであれば、コンサルタントにすべて任せるよりもコストをおさえることができます。
次に、導入のしやすさも重要なポイントです。
専門的な知識がなくてもすぐに使えるように、設定が簡単で、初日から基本的な操作ができるようなツールを選ぶと安心です。
たとえば、画面の案内に従って必要な情報を入力するだけで、台帳や記録が自動でつくられるしくみがあると、担当者の負担も大きく減らせます。
費用がわかりやすく、すぐに使いはじめられるクラウド型ツールを選ぶことが、Pマークの運用を長く続けるためのポイントになります。
5.まとめ
今回は、Pマーク運用における課題と、それを解決する手段としてのクラウド型管理ツールについて解説しました。
Pマークは取得後の運用負担やコストの高さ、不要なルールの増加といった理由から、運用を断念する企業も少なくありません。
しかし、クラウドサービスを活用すれば、情報の一元管理、アクセス性の向上、コスト削減、セキュリティ強化など、さまざまなメリットを得ることができます。
とくに「Pマークアシスト」のようなツールは、専門知識がなくても使いやすく、必要な書類や記録を効率よく管理できる仕組みが整っています。
「本業と両立できない」「更新のたびに時間とお金がかかる」といったお悩みをお持ちの方は、クラウド型Pマーク管理ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
現在、2週間の無料トライアルを実施中です。この機会にぜひお試しください。
ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!
認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。
経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。
▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間
- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間
- 審査資料の準備:20時間→0.5時間
認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。
Pマーク(プライバシーマーク)・ISOの認証・更新も安心
認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!
信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!
一目でわかる
認証パートナーのサービスご説明資料
8,000社以上の支援実績に裏付けされた、
当社サービスの概要を紹介しております。
資料の内容
- ・一目でわかる『費用』
- ・一目でわかる『取得スケジュール』
- ・一目でわかる『サポート内容』
Pマーク(プライバシーマーク)認証パートナー
サービスのご案内
認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。
お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。
-
Pマーク
個人情報保護マネジメントシステム
高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。
認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -
ISO9001
品質マネジメントシステム
品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。
認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -
ISMS・ISO27001
情報セキュリティマネジメントシステム
情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。
認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -
ISO14001
環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。
認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -
ISO27017など各種対応規格
ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。
ISO27017など各種対応規格ページへ -
複数規格の同時取得
ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください
複数規格の同時取得ページへ
- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.