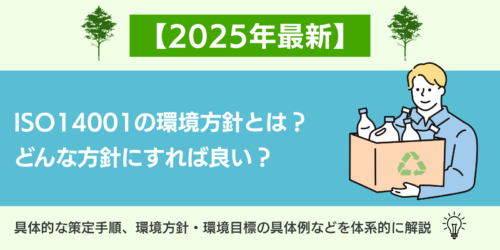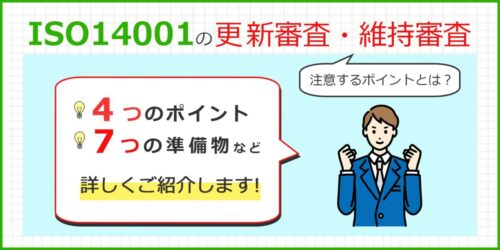2025年5月15日
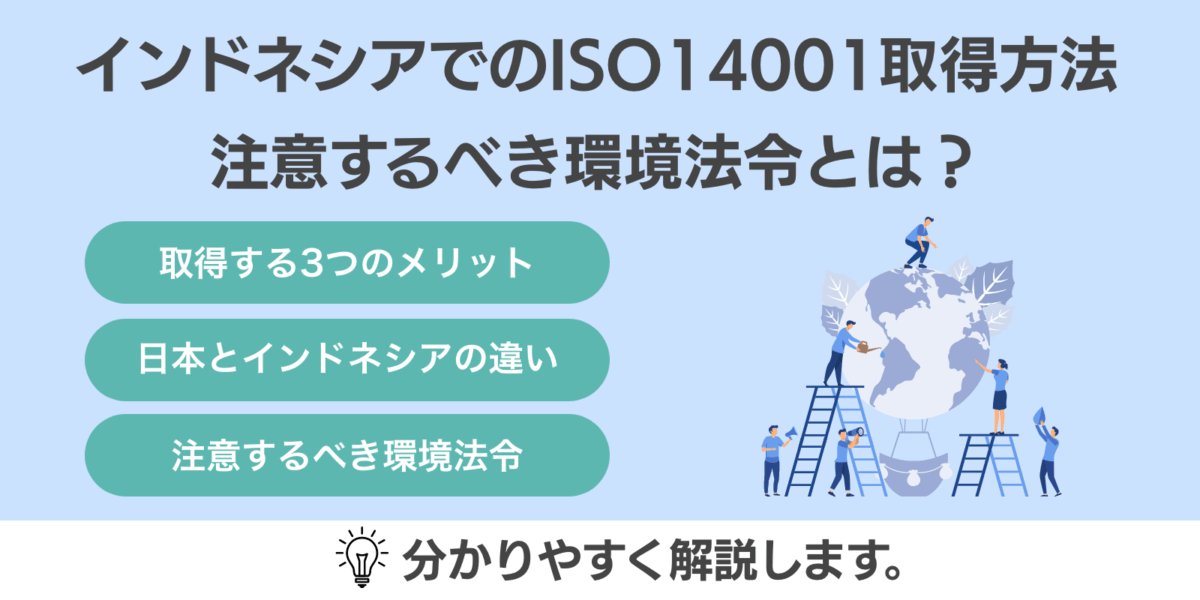
目次
Close
- 1.インドネシアでISO14001が必要な理由
- 2.インドネシアでISO14001を取得する3つのメリット
- (1)企業価値の向上
- (2)法令遵守の促進
- (3)従業員の環境意識の向上
- 3.インドネシアでISO14001を取得する3つのデメリット
- (1)マニュアルや記録を作成する手間がかかる
- (2)取得のために費用がかかる
- (3)高すぎる理想が社員の共感を遠ざける
- 4.「日本のISO」と「インドネシアのISO」の違い
- 5.ISO14001の取得で要求されている6つのこと
- (1)環境方針
- (2)環境目標
- (3)環境側面
- (4)遵守義務・遵守評価
- (5)緊急事態への取り組み
- (6)その他の必要な文書・活動
- 6.インドネシアでISO14001取得の際に注意するべき環境法令
- 7.インドネシアでのISO14001取得の流れ
- (1)組織内体制の確立
- (2)取得までの計画を立てる
- (3)外部のコンサルサポートを受けるか検討する
- (4)品質マネジメントシステムを構築する
- (5) ISO14001の要求事項に沿って運用を開始する
- (6) 審査機関に申請する
- (7) 審査を受ける
- (8) ISO14001認証の取得完了
- 8.インドネシアでのISO14001認証の取得にかかる費用相場
- (1)審査にかかる費用相場
- (2)審査以外にかかる費用
- 9.まとめ
「インドネシアでISO14001を取得したいけど、何から始めればいいのか分からない」
結論からお伝えすると、ポイントを押さえれば、インドネシアでもISO14001の取得は十分に可能です。
なぜなら、認証のしくみや流れは世界共通であり、現地の特徴さえ理解していれば、計画的に進められるからです。
この記事では、認証の基本から、必要な準備、費用の相場、現地の審査事情、コンサルの活用法まで、解説しています。
読み終えるころには、「何をすればいいか」がハッキリわかり、次にとるべき行動が見えてきます。
インドネシアでのISO14001取得に向けて、ぜひ、最後まで読んでみてください。
1.インドネシアでISO14001が必要な理由

インドネシアで事業を行う企業にとって、ISO14001の取得は年々重要性を増しています。その背景には、環境保護への社会的関心の高まりと、政府による法制度の強化があります。
同国では、2009年法律第32号「環境保護と環境管理に関する法律」や、2014年政府規則第101号「有害・有毒物質(B3)廃棄物管理に関する規則」※など、環境に関する厳しい法令が整備されています。また、環境影響評価(AMDAL)の提出が義務づけられており、事業の種類や規模によっては非常に高度な環境対応が求められます。
※インドネシア 有害廃棄物規制 | EnviXから引用
こうした中、ISO14001を取得している企業は、環境リスクに対応できる体制を整えていると判断され、当局や取引先からの信頼を得やすくなります。
インドネシアの国家統計局(BPS)のデータによれば、ISO 14001(SNI ISO 14001)認証を取得した企業数は以下のように増加しています:
- 2019年:2,125社
- 2020年:2,381社
- 2021年:2,381社
このような認証取得数の増加は、企業が環境規制への対応や国際的な取引要件への適合を重視していることを表しています。
さらに、環境配慮型の製品や経営が重視される国際市場では、認証の有無が企業の競争力に直結します。ISO14001の導入は、単なる法令対応にとどまらず、持続可能な成長と信頼の獲得に向けた戦略的な投資だと言えるでしょう。
2.インドネシアでISO14001を取得する3つのメリット
インドネシアでISO14001を取得することで得られる主なメリットは、大きく分けて3つあります。
- 企業価値の向上
- 法令遵守の促進
- 従業員の環境意識の向上
これらを知らずに認証取得を進めてしまうと、手間や費用ばかりが先行して、思ったほどの効果を得られない恐れがあります。ひとつずつ見ていきましょう。
(1)企業価値の向上
インドネシアでISO14001を取得することは、企業価値の向上につながります。
なぜなら、環境への配慮を国際的な基準に基づいて実践していることを第三者の認証によって示せるため、社会的信頼が高まり、企業の評価につながるからです。
同国では近年、持続可能な開発や環境保護への関心が高まっており、企業に対しても環境への取り組みが厳しく問われるようになっています。
ISO14001の取得は、単なる制度遵守の証明にとどまらず、環境リスクを計画的に管理し、継続的な改善を行っていることを公的に示す手段にもなるのです。
(2)法令遵守の促進
ISO14001を導入すると、インドネシアにおける法令遵守の体制が自然と整います。
なぜなら、環境保護に関する法律の把握と対応が、仕組みとしてあらかじめ組み込まれているからです。
現地では、2009年法律第32号「環境保護と環境管理に関する法律」や2014年政府規則第101号「有害・有毒物質(B3)廃棄物管理に関する規則」など、企業が対応すべき環境関連法が次々と施行され、法令の数や内容も年々複雑になっています。こうした変化を現場任せで対応し続けるのは困難です。
ISO14001では、該当する法令を洗い出して一覧化し、定期的に更新、確認する仕組みが求められます。
これにより、法令違反のリスクを未然に防ぐだけでなく、行政からの信頼や対外的な信用の維持にもつながります。
(3)従業員の環境意識の向上
ISO14001の導入は、従業員の環境意識を高める上でとても有効です。
規格に沿って業務プロセスを見直すことで、日々の業務の中で「環境への影響を考える」習慣が自然と育まれるからです。
この仕組みには、教育や訓練、内部監査といった取り組みが組み込まれており、全社員が共通の基準や目標を意識するようになります。
単なるマニュアル対応ではなく、自ら課題に気づき、行動を起こす力が育まれる点が大きな特徴です。
たとえば、大塚製薬工場では、全従業員を対象にeラーニングを活用した環境教育を定期的に実施しています。
2023年には、海外グループ会社(インドネシア)の優れた環境取り組み事例を共有し、従業員の環境意識向上を図っています。
参考:株式会社大塚製薬工場「環境マネジメント」
このように、ISO14001は単なる制度の枠を超えて、従業員一人ひとりの意識や行動を変えていく仕組みになっています。
環境経営を実現するための第一歩として、多くの企業で導入が進められているのもその効果の表れといえるでしょう。
3.インドネシアでISO14001を取得する3つのデメリット
インドネシアでISO14001を取得する際のデメリットは、以下の3つです。
- マニュアルや記録を作成する手間がかかる
- 取得のために費用がかかる
- 高すぎる理想が社員の共感を遠ざける
後悔のない判断をするためにも、ていねいに解説をしていきます。
(1)マニュアルや記録を作成する手間がかかる
ISO14001を導入する上で、多くの企業が最初に直面するのが、文書の整備に関する負担です。
環境マネジメントシステムでは、手順書やマニュアル、業務記録など、多くの文書を作成・管理することが求められます。
これらの書類は、単に形式を整えるだけでなく、実際の業務と矛盾がないように内容をすり合わせる必要があります。
そのため、担当者が業務フローを細かく把握しながら作成を進めることになり、慣れないうちは大きな負担と感じる場面も少なくありません。
たとえば、現場での作業手順を文書化する際には、実際の運用と乖離しないよう関係者との確認作業が必要になります。
加えて、記録は定期的に更新・保存する義務があるため、継続的な管理体制の構築も避けて通れません。
株式会社トーマツ環境品質研究所の報告では、ISO 14001の導入において「文書化の複雑さ」が主要な障壁の一つとして挙げられています。特に中小企業(SMEs)では、限られたリソースの中で文書の作成・管理を行うことが困難であると報告されています。
しかし、整備された文書は後の業務改善や教育にも活用できるため、短期的な負担を将来の資産に変えるという意識が重要です。
(2)取得のために費用がかかる
ISO14001を取得するには、相応のコストが伴います。
初期段階では、現状の確認やマニュアルの整備、社内体制の構築に時間と労力が必要となり、専門家の支援を受ける場合はコンサルタント費用も発生します。
インドネシアでは、現地語での文書対応や法制度への理解も求められるため、外部のサポートが欠かせない場面もあるでしょう。
これに加えて、審査機関への申請費や認証後の維持管理にも継続的な出費が必要です。
たとえば、定期的な内部監査や改善活動にあたるスタッフの確保、再認証にかかる費用などが挙げられます。
これらを踏まえると、導入後も一定の資金と人手を投じ続ける体制が欠かせません。
中小企業にとっては大きな負担となることもありますが、その一方で、環境対応を重視する顧客や海外取引の拡大につながる可能性もあります。
目先の費用だけでなく、将来の価値創出まで視野に入れた判断が求められます。
(3)高すぎる理想が社員の共感を遠ざける
ISO14001を導入し、環境経営を進めるうえで大切なのは、社員と歩調を合わせて取り組むことです。
なぜなら、理想だけを掲げても、現場の理解や共感がなければ継続的な改善は難しいからです。
経営層は「地球環境のためにすぐ行動を」と考えるかもしれませんが、現場では日々の業務で手一杯ということも多くあります。
無理な目標や一方的なルールは、かえって現場の反発ややる気の低下を招くリスクがあります。せっかくの取り組みも、共感が得られなければ長続きしません。
だからこそ、まずは社員の声を聞きながら、現実的な目標を一緒に考えていく姿勢が重要です。
4.「日本のISO」と「インドネシアのISO」の違い
ISO14001は国際的な規格であるため、基本的な考え方や要求事項に大きな違いはありません。
しかし、実際の運用や現場対応には、国ごとの事情が反映されることがあります。
日本では、制度や手順が細かく整っており、文書管理や内部監査の精度も比較的高い傾向があります。
一方、インドネシアでは、制度の成熟度や教育水準、インフラの整備状況などが異なるため、計画通りに進めることが難しい場面もあるようです。
たとえば、現場の担当者に対して日本と同じレベルの文書管理を求めても、十分に理解されないことがあります。
また、日常的な記録やルールの実行が、人に依存してしまうケースも見られます。
こうした点では、運用ルールや指導方法を現地の実情に合わせて工夫することが必要です。
さらに、審査機関やコンサルタントの支援体制も国によって異なります。
日本のように認証取得の実績が豊富な国とは異なり、インドネシアでは審査員の力量にばらつきがあることも否めません。
形式は同じでも、背景や前提条件が違えば、進め方や優先すべき対応も変わってきます。それぞれの国に合った方法で、柔軟に運用していくことが大切です。
5.ISO14001の取得で要求されている6つのこと
ISO14001を取得する際に求められる基本的な取り組みは、大きく分けて6つあります。
- 環境方針
- 環境目標
- 環境側面
- 遵守義務・遵守評価
- 緊急事態への取り組み
- その他の必要な文書・活動
わかりやすく整理していますので、ぜひご活用ください。
(1)環境方針
ISO14001における最も基本的な要求の一つが「環境方針」の策定です。
これは企業が環境に対してどのような姿勢で取り組んでいくのかを内外に示すものであり、組織全体の判断基準にも直結します。
環境方針には、法令遵守や汚染の予防、資源の有効活用、継続的改善への取り組みなどが含まれます。
抽象的な表現ではなく、自社の事業内容や地域性に合わせた具体性のある内容が求められる点も特徴です。
策定後は、全社員がその内容を理解し、日常業務に反映できるようにする必要があります。
方針そのものをポスターやイントラネットで共有するだけでなく、研修や朝礼などを通じて浸透させる工夫も不可欠です。
(2)環境目標
「環境目標」は、企業が環境に対してどのような成果を上げようとしているのかを示すものです。
目標の内容は、事業の規模や地域特性、製品の特性などに応じて決定されます。
たとえば、廃棄物の削減、電力使用量の抑制、リサイクル率の向上などが挙げられます。
重要なのは、数値や期限を明確にし、誰がどのように取り組むかが具体的にわかる状態にすることです。
単なる理想論やスローガンではなく、達成可能でありながらも意欲的な内容が求められます。
また、設定された目標は定期的に評価され、達成状況に応じて見直しや改善を行っていく必要があります。
(3)環境側面
ISO14001では、企業が自らの活動を通じて環境に与える影響を正確に把握し、管理することが求められています。
その基礎となるのが「環境側面」の特定です。
これは製品やサービス、業務プロセスなどを通じて環境に何らかの変化を引き起こす要因を意味します。
たとえば、エネルギーの使用、水の排出、騒音、廃棄物の発生といった事象は、環境側面として扱われます。
これらの要素が環境に与える影響の大きさを評価し、環境に重大な影響を及ぼすと判断されたものを重点的に管理していく必要があります。
(4)遵守義務・遵守評価
企業が関係する法令やその他の要求事項を正確に把握し、それを守ることを「遵守義務」と呼ばれています。単に理解するだけでなく、実際の業務で守られているかどうかを定期的に確認することが必要です。
たとえば、インドネシアの環境関連法には、大気や水質、廃棄物、騒音、化学物質などに関する規制が含まれています。
こうした法令を見落とせば、意図せず違反に至る可能性もあるため、定期的な見直しが不可欠です。
さらに、契約書や業界の自主基準なども「その他の要求事項」に含まれます。
これらも対象として整理し、現場と連携しながら、実施状況を点検することが重要です。
遵守評価は、一覧表や監査チェックを用いて行われ、違反や不備が見つかった場合には、改善策を講じる必要があります。
ただし、形式だけの評価に終わるとなく、現場の運用と照らし合わせて行動につなげていく視点が求められます。
(5)緊急事態への取り組み
ISO14001では、突発的な事故や自然災害といった緊急事態への備えが必須とされています。
環境への重大な影響を最小限に抑えるために、事前の準備と社内体制の整備が欠かせません。
緊急事態とは、火災、化学物質の漏洩、設備の破損、停電、大規模な自然災害など、通常業務を著しく妨げる事象を指します。
これらに対して、企業は対応手順をあらかじめ定め、必要な情報を従業員に周知しておくことが求められます。
単なる手順書の整備にとどまらず、定期的な訓練や模擬対応を実施し、いざという時に迅速な行動が取れるようにしておくことが重要です。
(6)その他の必要な文書・活動
ISO14001の運用には、環境方針や目標に関する書類以外にも多くの文書や活動が求められます。
たとえば、教育訓練の記録、外部とのコミュニケーション記録、文書の管理手順、変更履歴、内部監査の実施記録などが挙げられます。
さらに、環境影響に関する監視・測定の記録や、遵守評価に関する資料も必要です。
それぞれが「何を・誰が・どのように・いつ実施したか」を明確に示す形式で管理されなければなりません。
活動面では、内部監査の実施とその結果に基づく是正処置、マネジメントレビューによる振り返り、継続的改善の取り組みなどが含まれます。
6.インドネシアでISO14001取得の際に注意するべき環境法令
インドネシアでISO 14001を取得する際に注意すべき主要な環境法令は以下のとおりです。
- 環境保護法(UU No. 32/2009):環境汚染の防止や資源管理を規定。環境影響評価(AMDAL)が必要。
- 廃棄物管理法(UU No. 18/2008):廃棄物の適切な収集、処理、リサイクルが義務付けられています。
- 大気汚染管理法(PP No. 41/1999):大気汚染物質の排出基準を遵守する必要があります。
- 水質管理法(PP No. 82/2001):排水基準を守り、適切に水質を管理する必要があります。
- 化学物質管理法(Permen LH No. 12/2009):有害物質の適切な取り扱いと管理が求められます。
- エネルギー管理法(UU No. 30/2007):エネルギー効率の向上と省エネルギー対策が奨励されています。
これらの法令を遵守することが、ISO14001認証取得のためには不可欠です。
7.インドネシアでのISO14001取得の流れ
インドネシアでISO14001を取得するまでの基本的な流れは、大きく分けて7つのステップに整理できます。
- 組織内体制の確立
- 取得までの計画を立てる
- 外部のコンサルサポートを受けるか検討する
- 品質マネジメントシステムを構築する
- ISO14001の要求事項に沿って運用を開始する
- 審査機関に申請する
- 審査を受ける
- ISO14001認証の取得完了
この流れを知らずに進めてしまうと、必要な準備が漏れたり、審査で想定外の指摘を受けたりする可能性もあるため、ていねいに見ていきましょう。
(1)組織内体制の確立
インドネシアでISO14001を取得するためには、まず社内の体制を整えることが必要です。
誰がどのような役割を担うのかをはっきりさせないと、うまく進みません。
最初にやるべきことは、会社としての方針を明確にすることです。
経営層が「環境への取り組みを本気で進める」という姿勢を示し、それを全社員に伝えることが出発点となります。
次に、実際に動かすチームや担当者を決めていきましょう。
たとえば、環境マネジメントの計画を立てる人、現場で実行する人、進み具合を確認する人など、それぞれの役割を分けておく必要があります。
このように、社内でしっかりと役割と流れを決めておくことが、ISO14001の運用を安定させるためのスタート地点となります。
(2)取得までの計画を立てる
ISO14001を取得するためには、あらかじめ全体の計画を立てることが欠かせません。
行き当たりばったりで進めてしまうと、手戻りや混乱が発生しやすくなります。
まずは、現状の環境対応を整理することから始めましょう。
すでに行っている取り組みと、これから整えるべき内容を明確にすることで、優先順位が見えてきます。
次に、取得までのスケジュールを決めていきます。
文書の整備や社員への教育、内部監査、外部審査など、やるべきことを時期ごとに分けて段階的に整理することが重要です。
加えて、必要な予算や人員の手配もこの段階で検討しておくと安心です。
コンサルタントに支援を依頼する場合には、早めに連絡を取り、スケジュール調整や支援内容の確認を行っておくとよいでしょう。
しっかりとした計画があると、社内の役割分担や進行管理もスムーズになります。
(3)外部のコンサルサポートを受けるか検討する
ISO14001を取得するうえで、外部コンサルタントのサポートを受けるかどうかは、早めに判断する必要があります。
とくに、社内に専門知識が不足している場合や、過去に取得実績がない場合は注意が必要です。
インドネシアでは、現地の法律や行政手続きに関する理解が欠かせません。
こうした背景を踏まえると、現地事情に詳しい支援者の存在が、計画を円滑に進める要因となることもあります。
たとえば、文書の整備や内部監査の準備において、何を優先すべきか迷う場面も出てくるでしょう。
インドネシアでのISO14001取得を目指すのであれば、日本語とインドネシア語に対応可能なコンサルタントを選ぶと、より効果的です。
外部の視点が加わることで、社内では気づきにくい問題点にも対処しやすくなります。
(4)品質マネジメントシステムを構築する
最初の段階では、業務の中にある環境リスクを洗い出し、担当ごとの役割を明確にする必要があります。
目標設定や手順書の整備、記録の管理などを通じて、社内で一貫した運用体制を整えていく必要があります。
ISO担当者の指名と認証取得の計画がまとまった段階で、次に進めるべきはマニュアルと手順書の作成です。
自社でゼロから取り組む場合、おおよそ3ヶ月程度の期間を見込んでおくと安心です。
一方で、外部サポートを活用する場合は、1ヶ月程度で形にすることもできるでしょう。
(5) ISO14001の要求事項に沿って運用を開始する
マニュアルや手順書を整えた後は、実際の運用段階に移ります。
ISO14001は、認証を取ることが目的ではなく、日常の業務に組み込んで継続的に改善を重ねていく仕組みです。
手順書が整い次第、運用を開始します。
インドネシアにおいては、運用開始までにおおよそ6ヶ月ほどかかるのが一般的ですが、外部のサポートをうまく活用すれば、1〜3ヶ月で本格的な運用に入ることも可能です。
運用の基本は、決められた手順に従って業務を実施し、その結果を記録として残すことにあります。
環境活動は一部の担当者に任せるのではなく、組織全体で取り組むことが必要です。
また、内部監査やマネジメントレビューも重要な要素です。
形式的なチェックにとどまらず、現場の声を反映した見直しを重ねることで、システム全体が育っていきます。
(6) 審査機関に申請する
ISO14001の運用が安定し、必要な準備が整ったら、認証取得に向けて審査機関へ申請します。
この段階では、これまでの取り組みが外部の目によって評価されることになります。
申請にあたっては、認証機関の選定が重要です。
インドネシア国内には複数の審査機関があり、それぞれの対応方針や審査の厳しさ、審査員の経験に違いがあります。
対応言語や費用、審査期間も異なるため、事前の比較検討が欠かせません。
提出する書類には、マニュアル、運用記録、内部監査結果、改善報告などが含まれます。
審査では、それらの記載と実際の運用が一致しているかどうかが確認されます。
不備があった場合、是正対応や再提出を求められることもありますが、準備段階での見直しによって回避できることも少なくありません。
(7) 審査を受ける
審査機関に申請を終えたあとは、ISO14001の審査を受ける段階に進みます。
この審査は、企業が構築した環境マネジメントシステムが、国際規格の要求を満たしているかを第三者が確認する重要な工程です。
審査は一般的に二段階で行われます。
1次審査では、提出されたマニュアルや記録類が整っているか、文書上の不備がないかを中心に確認されます。
その後、2次審査として実地審査が実施され、実際の運用が記録と一致しているか、社員が手順を理解して行動しているかといった点が見られます。
インドネシアでは、審査員が複数の言語に対応していない場合もあるため、必要に応じて社内通訳の準備が求められることもあります。
また、現場が複数拠点にわたる企業では、審査日程が数日間におよぶことも珍しくありません。
審査中に指摘された事項は、記録としてまとめられ、後日是正措置の報告が求められる場合もあります。
ただし、これは不合格という意味ではなく、改善の機会として前向きに捉えることが大切です。修正には約1ヶ月かかることがあるため、余裕を持ったスケジュールで取り組みましょう。
(8) ISO14001認証の取得完了
最終審査を通過し、必要な是正措置も完了すれば、いよいよISO14001の認証取得が正式に確定します。
この時点で、自社の環境マネジメントシステムが国際的な基準に適合していることが、第三者機関により公式に認められたことになります。
認証書には、企業名、対象範囲、認証日、有効期間などが記載され、対外的な信用の証として活用できます。
取引先や関係機関に対しても、環境への取り組みを積極的に行っている企業としての評価が得られるようになるでしょう。
ただし、取得はあくまで通過点に過ぎません。
環境目標の見直しや内部監査の継続、教育の実施など、日々の運用を維持・改善していくことが本来の目的となります。
インドネシアにおいても、認証の有無は公共調達や海外取引の場面で重要視されるケースが増えています。
社内の努力が正式に評価されることで、従業員の意識向上や次の改善サイクルへの意欲にもつながっていくでしょう。
8.インドネシアでのISO14001認証の取得にかかる費用相場
インドネシアでISO14001認証を取得する際に必要となる費用は、大きく分けて2つに整理できます。
- 審査にかかる費用相場
- 審査以外にかかる費用
費用の全体像を把握し、無理のない計画を立てるために、ぜひ参考にしてください。
(1)審査にかかる費用相場
インドネシアでISO14001の認証を取得する際の費用は、選ぶ認証機関の種類や企業規模によって大きく異なります。
認証機関は主に、インドネシア国内でKAN(国家認定機関)により認定されたものと、海外の認定機関(UKAS、EGACなど)に分かれています。
一般的に、海外の認定機関を利用する場合、料金は約2,500万ルピア(約24万円)からが相場とされており、国内のKAN認定機関と比べて高めの設定となる傾向があります。
一方、KAN認定の国内機関であれば、おおよそ2,000万ルピア(約19万円)前後から申請が可能です。
ただし、国内であっても著名で大規模な認証機関を選んだ場合、料金が逆に高くなる例も見られます。
さらに、KANや海外の認定を受けていない認証機関を利用する場合、相場は大きく下がり、800万〜1,000万ルピア(約7.6万〜9.5万円)程度から対応しているところも存在します。
料金の安さだけを基準に選ぶと、認証の信頼性や将来の維持管理に影響を与える可能性もあるため、注意が必要です。
費用だけでなく、審査の質、サポート体制、言語対応、審査員の経験なども含めて総合的に判断しましょう。
(2)審査以外にかかる費用
ISO14001の認証取得においては、審査費用のほかにも複数の費用が発生します。
中でも代表的なのが、外部コンサルタントへのサポート費用です。
ISOの規格は専門的な要件が多く、初めて取り組む企業では内部だけで対応するのが難しい場面も少なくありません。
そのため、制度設計や文書作成、内部監査の準備などを支援するために、外部の専門家に業務を委ねるケースが多く見られます。
コンサルタント費用の相場は、依頼する会社やサービスの範囲によって異なりますが、ローカルのコンサルタントであれば比較的安価に始めることが可能です。
一般的には、費用は1,800万ルピア(約17万円)からが目安とされており、フルサポート型のプランでは数千万ルピア(数十万円)に達することもあります。
そのほかにも、社内研修の実施費用、印刷や資料作成の経費、審査準備のための内部リソースの確保といった間接的なコストも見逃せません。
さらに、年次更新審査や是正対応が発生した場合には、そのたびに新たな工数や経費がかかる可能性があります。
予算を見積もる際は、審査費用だけに注目するのではなく、構築から維持・更新に至るまでの総合的な費用を把握しておくことが重要です。
9.まとめ
今回は、ISO14001の基本的な概要から、インドネシアで取得する際の具体的な流れ、必要となる書類や費用、そしてメリット・デメリットまでを総合的に解説しました。
ISO14001は単なる国際認証ではなく、環境への配慮を事業に取り入れ、企業の信頼性や競争力を高めるための重要な仕組みです。
とくにインドネシアでは、KAN認定や海外認定など複数の審査機関が存在しており、それぞれの費用や審査方針を理解したうえで適切な選択をすることが求められます。
また、構築・運用にあたっては、マネジメント体制の整備、従業員への教育、内部監査の実施、文書管理の徹底といった取り組みが欠かせません。
ISO14001の取得には一定のコストと工数が必要ですが、環境対応を重視する企業との取引拡大や、組織内の意識改革にもつながる価値ある投資といえるでしょう。
「現地でどうやって進めればよいかわからない」
「何にどれだけの費用がかかるのか不安だ」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、認証パートナーにご相談ください。
当社のインドネシアにおけるサービスサイトはこちらになります。
現地事情に精通したスタッフが、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適な取得プランをご提案いたします。
ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!
認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。
経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。
▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間
- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間
- 審査資料の準備:20時間→0.5時間
認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。
ISO・Pマーク(プライバシーマーク)の認証・更新も安心
認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!
信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!
一目でわかる
認証パートナーのサービスご説明資料
8,000社以上の支援実績に裏付けされた、
当社サービスの概要を紹介しております。
資料の内容
- ・一目でわかる『費用』
- ・一目でわかる『取得スケジュール』
- ・一目でわかる『サポート内容』
ISO14001認証パートナー
サービスのご案内
認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。
お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。
-
Pマーク
個人情報保護マネジメントシステム
高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。
認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -
ISO9001
品質マネジメントシステム
品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。
認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -
ISMS・ISO27001
情報セキュリティマネジメントシステム
情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。
認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -
ISO14001
環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。
認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -
ISO27017など各種対応規格
ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。
ISO27017など各種対応規格ページへ -
複数規格の同時取得
ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください
複数規格の同時取得ページへ
- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.