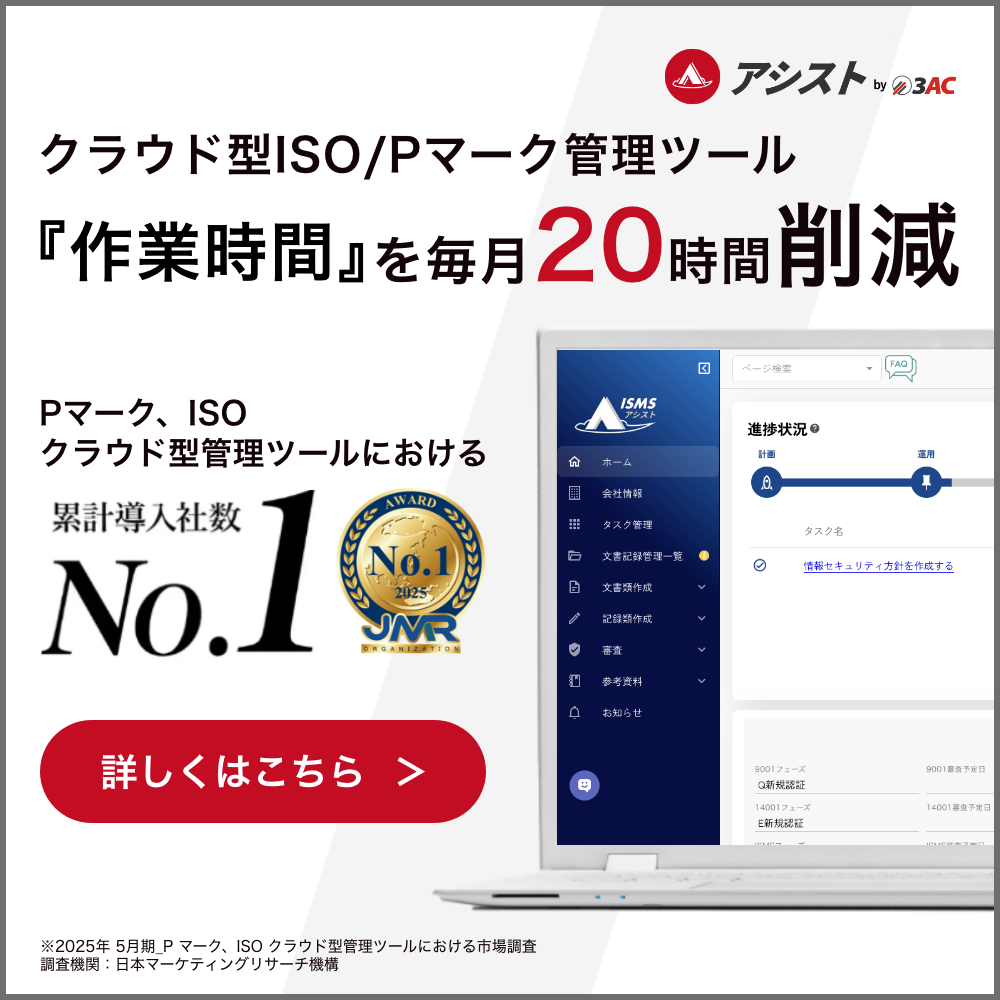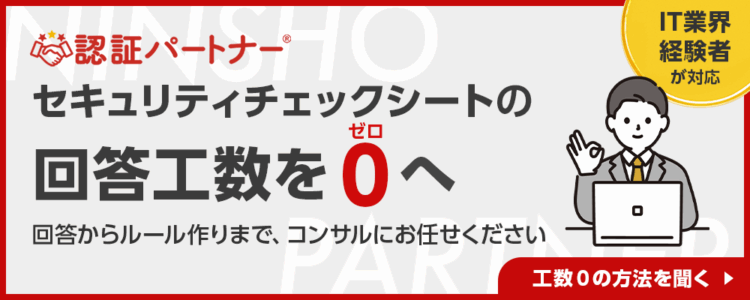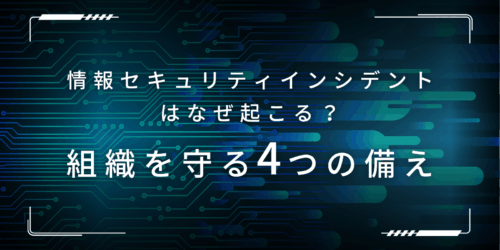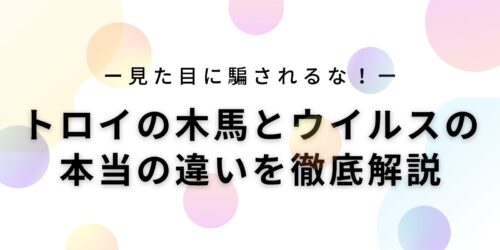完全性とは?失われる3つの原因と今日から始められる8つの対策
2025年5月16日
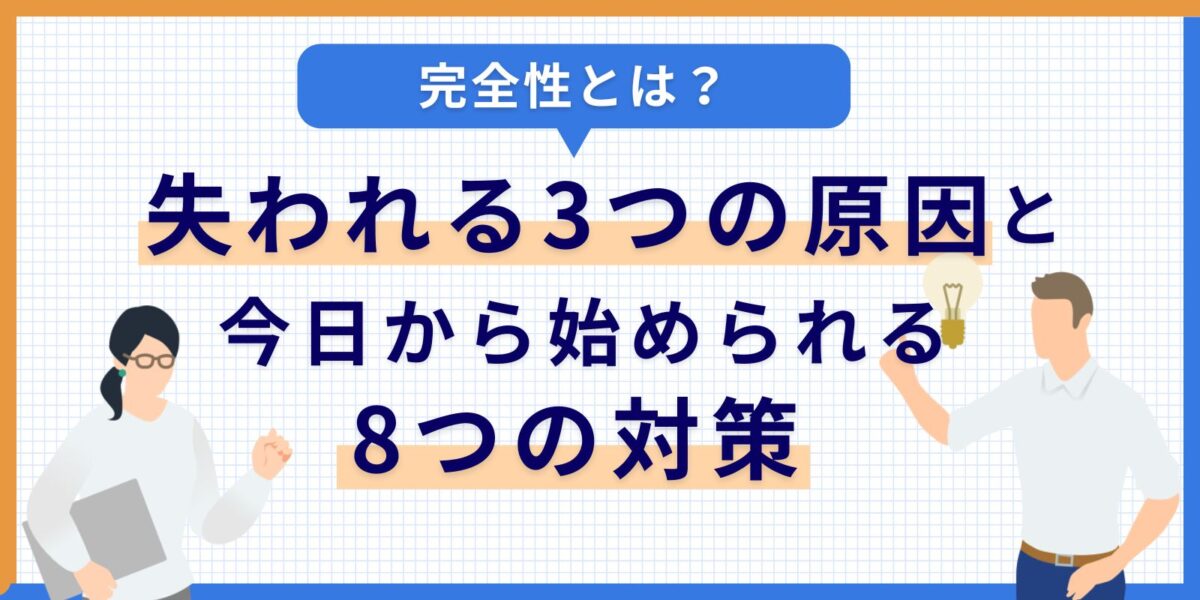
目次
Close
- 1.完全性とは「情報が正しいままの状態」であること
- 2.完全性が失われてしまう3つの原因
- (1)人的ミス(ヒューマンエラー)によるデータの誤入力や削除
- (2)システムの設定ミスや不具合によるデータ破損
- (3)外部からの不正アクセスやサイバー攻撃による改ざん
- 3.完全性を確保するための具体的な8つの対策
- (1)データのバックアップ
- (2)アクセス権限の管理
- (3)変更履歴の記録
- (4)デジタル署名の導入
- (5)チェックサムやハッシュ関数
- (6)データ入力・編集時の再確認
- (7)セキュリティソフトの導入
- (8)バージョンの管理
- 4.完全性を守るために組織的が取り組むべき3つの施策
- (1)情報セキュリティポリシーに完全性の考え方を盛り込む
- (2)データを守る意識を全社員に広げるための教育の実施
- (3)外部の専門機関による定期的なチェック
- 5.まとめ
「完全性って何?」「どうすれば守れるのだろう?」
そんな悩みを抱えていませんか。
たとえば、会社の大切な情報を誰かがこっそりデータを書きかえたり、知らないうちに間違った情報が入ってしまったら困りますよね。
これを防ぐために大切なのが「完全性」という考え方です。
つまり、完全性とは「情報を正しく保つこと」であり、それを守るには技術とルールの両方が対策が必要です。
なぜなら、システムや書類が正しく使われていても、ルールがゆるかったり、人のうっかりミスがあると、情報はすぐに変更されてしまうからです。
この記事では、完全性の意味やよくあるトラブル、さらに今すぐできる対策までを解説していきます。
最後まで読めば、あなたの会社やチームの大切な情報をどう守るべきかがわかるようになります。
情報を安全に使い続けるために、ぜひ最後まで読んでみてください。
1.完全性とは「情報が正しいままの状態」であること
完全性とは、「情報が正しくて、勝手に書きかえられたり、消されたりしていない状態のこと」をいいます。
つまり、誰かの手違いや悪意によって、データの内容が変わらないかどうかを守ることです。こうした「正しい情報」をきちんと保つことは、毎日の仕事や判断にとってとても大切です。
なぜなら、もし間違った情報を元に判断してしまえば、誤った対応をしてしまうからです。
たとえば、伝票の金額が書き変わっていたら請求ミスが起きたり、顧客の住所が間違っていたら荷物が届かないなどのトラブルが発生します。
具体的には、顧客の住所が「東京都港区新橋1丁目10-10」と登録すべきところを、「東京都港新橋1丁目10-10」と誤って記載していた場合、番地は正しくても「港区」が「港」と省略されていることで、配送業者がエリアを正確に特定できず、荷物が返送されてしまうケースがあります。
また、会社のホームページの内容が第三者に書きかえられてしまったら、企業の信用が大きく下がってしまうかもしれません。
このように、「どこも変わっていない」「安心して使える」状態を守ることが、完全性を保つことにつながります。
つまり完全性とは、ただデータを残しておくだけでなく、「使うときにも正しいままにしておくことが大切」だという考え方なのです。
2.完全性が失われてしまう3つの原因

完全性が失われるとされる理由は、大きく分けて3つあります。
- 人的ミス(ヒューマンエラー)によるデータの誤入力や削除
- システムの設定ミスや不具合によるデータ破損
- 外部からの不正アクセスやサイバー攻撃による改ざん
完全性が守られていないと、知らないうちに情報が間違っていたり、取引や業務に大きな影響が出てしまうおそれがあります。
一方で、こうした原因を理解していれば、事前に防ぐための対策をとることができ、トラブルの発生を減らすことも可能です。
順番に見ていきましょう。
(1)人的ミス(ヒューマンエラー)によるデータの誤入力や削除
データの完全性が失われる原因の一つが、人の操作ミス(ヒューマンエラー)です。
どれだけシステムが整っていても、人が関わる以上、入力や操作のミスはどうしても起きてしまいます。
たとえば、日付や金額を間違って入力したり、必要なデータを間違えて削除してしまったりすることがあります。
また、保存するつもりが上書きしてしまった、確認せずに「削除」を押してしまったなど、ちょっとした油断が原因になることも少なくありません。
こうしたミスは、特別なスキルがなくても誰にでも起こりうるため、油断は禁物です。
このように人的ミスは日常的に発生しやすく、気づかないまま進行することもあるため、完全性を守るうえでとくに注意が必要です。
(2)システムの設定ミスや不具合によるデータ破損
システムの設定ミスや動作のトラブルが原因で、データが破損してしまうことがあります。
このようなことが起きると、大切な情報が使えなくなったり、元に戻せなくなるおそれがあります。
たとえば、バックアップの設定が正しく行われていなかったために、障害発生時にデータを復元できなかったという事例があります。
情報処理推進機構(IPA)のガイドラインにおいても、ログ(システム内で起きた出来事を時系列で記録してくれる仕組み)の保存期間設定ミスにより、必要なログが自動的に削除され、障害発生時の原因調査が困難になるリスクが指摘されています。
こうした不具合は、利用者には見えにくいため、気づかないうちに完全性が損なわれていることがあるのです。
システムの不具合や設定ミスは、情報を正しい状態で保つうえで大きなリスクとなります。
(3)外部からの不正アクセスやサイバー攻撃による改ざん
外部からの不正アクセスやサイバー攻撃によって、データが書きかえられてしまうことがあります。このような攻撃は、情報の完全性が失われる最も深刻なケースの一つです。
インターネットでさまざまなデータがつながっている今の時代では、外からの攻撃によってシステムに入り込まれてしまうおそれがあります。
とくに会社や団体のホームページや顧客情報を扱うシステムは、攻撃の対象になりやすく、被害も大きくなることが多いです。
2024年6月8日、KADOKAWAグループはランサムウェア攻撃を受け、ドワンゴのファイルサーバーから個人情報が漏洩しました。攻撃の原因は、従業員のアカウント情報がフィッシングにより盗まれたことと推測されています。これにより、社内ネットワークへの侵入と情報漏洩が発生しました。
参照:ランサムウェア攻撃による情報漏洩に関するお知らせ
このように外部からの不正なアクセスや攻撃は、情報の正しさを根本から崩してしまう危険性が伴います。
そのため、パスワードの管理やウイルス対策ソフトの導入、システムの定期的な見直しなど、日ごろから備えておくことがとても大切です。
3.完全性を確保するための具体的な8つの対策
完全性を確保するための対策には、以下の8つあります。
- データのバックアップ
- アクセス権限の管理
- 変更履歴の記録
- デジタル署名の導入
- チェックサムやハッシュ関数
- データ入力・編集時の再確認
- セキュリティソフトの導入
- バージョンの管理
これらの対策を知らずにいると、気づかないうちに大切な情報が壊れたり、第三者に書き換えられたりして、業務や信頼に大きな影響が出るおそれがあります。
ひとつずつ解説していきます。
(1)データのバックアップ
情報の完全性を守るために、データのバックアップは最も基本で重要な対策のひとつです。
なぜなら、どれだけ注意していても、突然のトラブルで大切なデータが失われるリスクは避けられないからです。
たとえば、パソコンの故障、ソフトの不具合、誤操作、ウイルス感染などが原因で、必要なファイルが消えてしまうことは珍しくありません。こうした予期せぬ事態に備えておくには、日頃から自動的にバックアップを取る仕組みを整えることが欠かせないのです。
たとえば、Google ドライブやDropboxなどのクラウドサービスに保存先を設定しておくと、作業中に自動でバックアップされるようになります。
このとき、ファイルを「Dropbox」フォルダの中で編集すれば、常に最新の状態がクラウドに保存され、別のパソコンからもすぐにアクセスできます。
もしパソコンが突然壊れたとしても、クラウド上にデータがあれば、他の端末からログインしてファイルを取り出すことができます。
このように、バックアップは「万が一」のときの備えであり、情報の内容の正しさと安全性を保つことが可能になります。
できるだけ自動で、こまめに、複数の場所に保存する仕組みを作ることが確実な対策につながるのです。
(2)アクセス権限の管理
情報の正確さと安全性を保つためには、アクセス権限の管理が欠かせません。
なぜなら、誰でも自由にファイルを閲覧・編集できる状態では、うっかりした操作や悪意ある行動によって、重要な情報が変更・削除されてしまうリスクがあるからです。
たとえば、社内で共有されている「契約書フォルダ」が全社員にフルアクセスで開放されていた場合、誤ってファイルが削除されたり、本来関係のない社員によって内容が書き換えられる可能性があります。
これを防ぐには、フォルダやファイルごとに「閲覧のみ」「編集可」など、ユーザーごとに操作の範囲を制限することが重要です。
Windowsでは、フォルダの「プロパティ」から「セキュリティ」設定に進み、ユーザーごとにアクセス権限を調整できます。
Google ドライブのようなクラウドサービスでは、共有リンクの権限設定で「閲覧のみ」「コメントのみ」「編集可」など細かく設定可能です。
また、見落としがちなポイントとして、退職者や異動者のアカウント管理も挙げられます。
使われていないアカウントが残ったままになっていると、不正アクセスや情報漏洩の原因にもなりかねません。月に1度はアカウントの棚卸しを行い、不要なユーザーを削除する習慣をつけましょう。
このように、アクセス権限をきちんと管理することは、情報の正しさを守るだけでなく、社内の安全な運用にもつながります。「誰が、どこまでできるか」を整理することから始めてみましょう。
(3)変更履歴の記録
ファイルの変更履歴を記録しておくことも完全性を守るためにはとても重要です。
なぜなら、誰が、いつ、どのように変更を加えたのかを把握できれば、トラブル発生時に原因を特定しやすくなり、必要に応じて正しい状態に復元できるからです。
たとえば、社内で共有している取引先リストが、ある日突然内容が変わっていたとします。
変更履歴が残っていなければ、誰が書き換えたのかが分からず、どの時点の情報が正しいかを判断できなくなってしまいます。
一方で、履歴を確認できる仕組みがあれば、「〇月〇日に〇〇さんが〇〇列を編集」と把握でき、必要に応じて修正前の状態に戻すことも可能です。
このような履歴管理は、作業ミスへの備えとしてだけでなく、意図的な改ざんやトラブル時の責任所在の明確化にもつながります。
ExcelやGoogleスプレッドシート、WordやGoogleドキュメントには、変更履歴の自動保存機能が備わっています。とくにGoogleのツールは、ファイルを開いて「ファイル → 版の履歴」から簡単に確認可能です。
まずは、社内で共有している重要ファイルから、履歴機能が有効になっているかを確認してみましょう。
必要に応じて履歴を定期的に確認する習慣を持つことで、情報の完全性をより確実に保つことができます。
(4)デジタル署名の導入
情報の正しさや改ざんがないことを証明するのにデジタル署名はとても有効です。
紙の書類に押す印鑑のように、デジタルの世界でも「この内容が正しいことを確認しました」という証明が求められますが、その役割を果たすのがデジタル署名です。
たとえば、ある契約書の電子ファイルにデジタル署名がついていれば、それが本人によって作られ、途中で書きかえられていないことを第三者が確認できます。
仮に、誰かが内容を変更した場合、自動で「改ざんされました」と表示されるため、すぐに異常に気づけます。取引先との契約や請求書のやり取りなど、内容の信頼性が重要な場面ではとくに有効です。
実際には「GMOサイン」、「クラウドサイン」などの電子契約サービスを使えば、書類の送信から署名、保管までを簡単に行うことができます。無料プランもあるので、1通の契約書や覚書でテスト導入してみるのがおすすめです。
まずは、社内でやり取りしている重要な文書に、署名機能が使えるか確認するところから始めてみてください。
(5)チェックサムやハッシュ関数
データが正しく保たれているかを確認する方法として、「チェックサム」や「ハッシュ関数」もおすすめです。
どちらもファイルやデータが途中で書き換えられたり、壊れたりしていないかを確かめるための仕組みで、目に見えない改ざんや破損を正確に見分けることができます。
チェックサムとは、データの中身に基づいて計算された「合計値」のようなものです。
ファイルを送信する前にこの値を計算し、受け取った側でも同じように計算して、結果が一致するかを確認します。
一致すればデータは正しく届いており、一致しなければ途中でミスや改ざんがあった可能性があると判断できます。ファイル転送やダウンロード時の簡易的な整合性のチェックに使われることが多いです。
一方、ハッシュ関数は、データから一方向の計算によって「ハッシュ値」と呼ばれる短い文字列を作り出す方法です。
元のデータが1文字でも変われば、ハッシュ値もまったく異なるものになるため、改ざんの有無を正確に見分けることができます。
たとえば、ソフトウェアをダウンロードするときに、「ハッシュ値はこちら」と書かれているのを見たことがある方もいるかもしれません。
これは送られてきたファイルとダウンロードしたファイルが、まったく同じ内容であるかを利用者が確認できるようにしているのです。
このように、チェックサムやハッシュ値を活用することで、データの信頼性を自ら検証できるようになります。
ファイルを扱う際は、「正しく届いているか」「書き換えられていないか」を確認する手段として、積極的に活用してみてください。
(6)データ入力・編集時の再確認
データを入力・編集する際に、きちんと再確認を行うことが大切です。
どんなに慎重に作業していても、人の手による入力や修正にはミスはつきもの。そのため、「正しく入れたつもり」ではなく、「実際に正しく入っているか」を確認する仕組みが必要になります。
たとえば、売上金額を入力する際に「100,000円」と入力すべきところを「10,000円」としてしまうと、請求や収支の集計に大きな誤差が生まれます。
また、表計算ソフトで関数や計算式を使っている場合、一部のセルが意図せず上書きされていたり、空白のままになっていると、正しい集計ができません。
こうしたミスを防ぐには、入力後に別の人が確認する「ダブルチェック」や、入力値に対するエラーチェック機能を活用するとよいでしょう。Excelであれば「データの入力規則」を使って、数字以外は入力できないように制限をかけることができます。
日々の業務の中で確認の仕組みを取り入れることで、思わぬミスによるトラブルを未然に防ぐことが可能です。まずは、よく使う入力シートから「確認プロセス」を取り入れてみましょう。
(7)セキュリティソフトの導入
セキュリティソフトの導入は、情報の完全性を守るうえで欠かせない対策のひとつです。
なぜなら、外部からのウイルス感染や不正アクセスにより、重要なファイルが壊されたり、意図しない変更を加えられたりするリスクが常にあるからです。
たとえば、ある日パソコンを開いたらファイルがすべて開けなくなっていた、あるいは知らない第三者によって勝手にメールが送られていたという事例は珍しくありません。こうした攻撃の多くは、ウイルスやマルウェアといった悪意あるプログラムによるものです。
セキュリティソフトは、これらの脅威を自動で検知し未然に防ぐ役割を果たします。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「日常における情報セキュリティ対策」においても、企業に対してセキュリティソフトの導入が推奨されています。セキュリティソフトの導入と定期的なアップデートにより、ウイルス感染や不正アクセスによる情報漏洩等のリスクを大幅に軽減することができるからです。
業務用のパソコンには、最低限の対策として必ずセキュリティソフトを入れ、常に最新の状態に保つことが情報資産を守るうえで大切なのです。
(8)バージョンの管理
「バージョンの管理」を行うことも情報の完全性を守るためにはとても重要です。
バージョンとは、文書やファイルが更新されるたびに記録される「その時点の状態」のことです。
バージョンを正しく管理することで、誰が、いつ、どこを変更したのかを把握でき、誤操作や情報の食い違いを防ぐことができます。
たとえば、取引先との契約書を修正する際に、以前の内容を直接上書きしてしまうと、元に戻したいときにどこをどう修正したのか分からず、トラブルの原因になることもあります。
しかし、「契約書_第1版」「契約書_第2版」といったようにファイル名に版数や作成日を明記して保存しておけば、過去の状態にさかのぼることが可能です。
また、GoogleドキュメントやWordなどのツールには、自動でバージョン履歴を残す機能もあるため、誰が何を変更したかを簡単に確認できます。複数人での作業や外部との共有が必要な文書では、こうした機能を活用することで誤解や責任の所在の不明瞭さを避けることができます。
まずは、重要なファイルについて「日付」や「バージョン番号」をファイル名に入れて保存する習慣から始めてみましょう。「_v1」「_2025-04-22版」など、一定のルールで管理することで、履歴の追跡もよりスムーズになります。
4.完全性を守るために組織的が取り組むべき3つの施策
最後に、完全性を守るために組織としてどのように取り組むべきかについて、3つの施策をご紹介します。
- 情報セキュリティポリシーに完全性の考え方を盛り込む
- データを守る意識を全社員に広げるための教育の実施
- 外部の専門機関による定期的なチェック
ひとつずつ見ていきましょう。
(1)情報セキュリティポリシーに完全性の考え方を盛り込む
完全性を守るためには、情報セキュリティポリシーに「完全性」の考え方を明記しましょう。情報セキュリティポリシーとは、組織全体で情報をどう守るか、その方針やルールをまとめた文書を指します。
ポリシーとして明文化しておかないと、現場ごとに認識や対応がばらつき、結果的に情報の正確性が保てなくなるリスクがあります。
たとえば、「入力内容の二重チェックを義務づける」「変更履歴を必ず記録する」といった運用ルールをポリシーに明記することで、誰が担当しても同じ基準で情報が管理されます。
また、新たなシステムを導入する際にも、「完全性確保の設定項目を確認する」といったチェック体制を整えることで、設定ミスによるデータ改ざんのリスクも低減できます。
つまり、完全性に関する方針をポリシーに含めておくことで、全社的な基準が明確になり、情報の正確さを守れるようになるのです。
(2)データを守る意識を全社員に広げるための教育の実施
完全性を守るためには、社員全員がデータを正しく扱う意識を持つことが欠かせません。
どれほど高度なシステムを導入していても、実際に情報を扱うのは人間です。意識が不十分であれば、ちょっとした操作ミスが重大な情報の損失や改ざんにつながってしまいます。
たとえば、メールの宛先を間違えて送信してしまったり、共有ファイルをうっかり上書きしてしまったといった人的ミスは、どの職場でも起こり得ます。このようなミスは、個々の情報に対する意識が不足しているとより発生しやすくなります。
そのためには、「なぜ情報を正しく扱う必要があるのか」「どのような操作がリスクになるのか」といった知識を伝える研修が有効です。さらに、実務でのミスを想定した演習やチェックリストを使えば、理解だけでなく行動にもつなげられます。
完全性の確保には、技術的な対策だけでなく、全社員が日々の業務の中で正しい行動を取れるようにする教育も不可欠です。
(3)外部の専門機関による定期的なチェック
情報の完全性を保つためには、社内の取り組みに加えて、外部の専門機関による客観的なチェックを取り入れることも有効です。
なぜなら、社内だけで対応していると、見慣れた業務の中でリスクを見逃してしまったり、慣れによって確認が甘くなったりすることがあるからです。
たとえば、ある部署でアクセス権限の設定ミスがあった場合でも、日常的に利用している社員には違和感がなく、誤設定に気づかれず放置されることがあります。
しかし、外部の監査機関が定期的にシステムの権限設定を確認すれば、こうした潜在的な問題を早期に発見し、改善につなげることができます。
外部チェックには、情報セキュリティ監査やISMSなどの認証審査、さらに実際に攻撃を試みるペネトレーションテスト(侵入テスト)などがあります。
これらを活用すれば、単なる内部管理にとどまらず、社外に対しても情報を正しく管理している組織であることを証明できます。
外部の視点を定期的に取り入れることで、見落としを防ぎ、情報の完全性を高い水準で維持するための有効な手段になるはずです。
5.まとめ
今回は、情報セキュリティにおける完全性の基本的な意味から、完全性が失われる主な原因、そして具体的な対策までを解説しました。
完全性とは、「情報が正確で、改ざんや誤りなく保たれている状態」のことです。
請求書の金額が書きかえられていたり、顧客情報に誤ったデータが入力されていた場合、業務の混乱や信用の失墜につながるおそれがあります。
こうしたリスクを防ぐためにも、完全性を守る仕組みを整えることは、企業にとって欠かせません。
ただし、完全性を確保するには、システム面の対策だけでなく、運用ルールやチェック体制の整備、社員教育など、組織全体での取り組みが必要です。
「うちの会社は、本当に正しく情報を管理できているだろうか?」
「気づかないところで、情報が変わってしまっていることはないだろうか?」
そんな不安をお持ちの方は、認証パートナーに一度ご相談ください。
専門スタッフが無料相談を通じて、お客様の実情やお悩みに合わせた最適な対応策をご提案いたします。
ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!
認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。
経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。
▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間
- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間
- 審査資料の準備:20時間→0.5時間
認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。
ISO・Pマーク(プライバシーマーク)の認証・更新も安心
認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!
信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!
一目でわかる
認証パートナーのサービスご説明資料
8,000社以上の支援実績に裏付けされた、
当社サービスの概要を紹介しております。
資料の内容
- ・一目でわかる『費用』
- ・一目でわかる『取得スケジュール』
- ・一目でわかる『サポート内容』
ISMS(ISO27001)認証パートナー
サービスのご案内
認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。
お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。
-
Pマーク
個人情報保護マネジメントシステム
高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。
認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -
ISO9001
品質マネジメントシステム
品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。
認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -
ISMS・ISO27001
情報セキュリティマネジメントシステム
情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。
認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -
ISO14001
環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。
認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -
ISO27017など各種対応規格
ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。
ISO27017など各種対応規格ページへ -
複数規格の同時取得
ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください
複数規格の同時取得ページへ
- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.