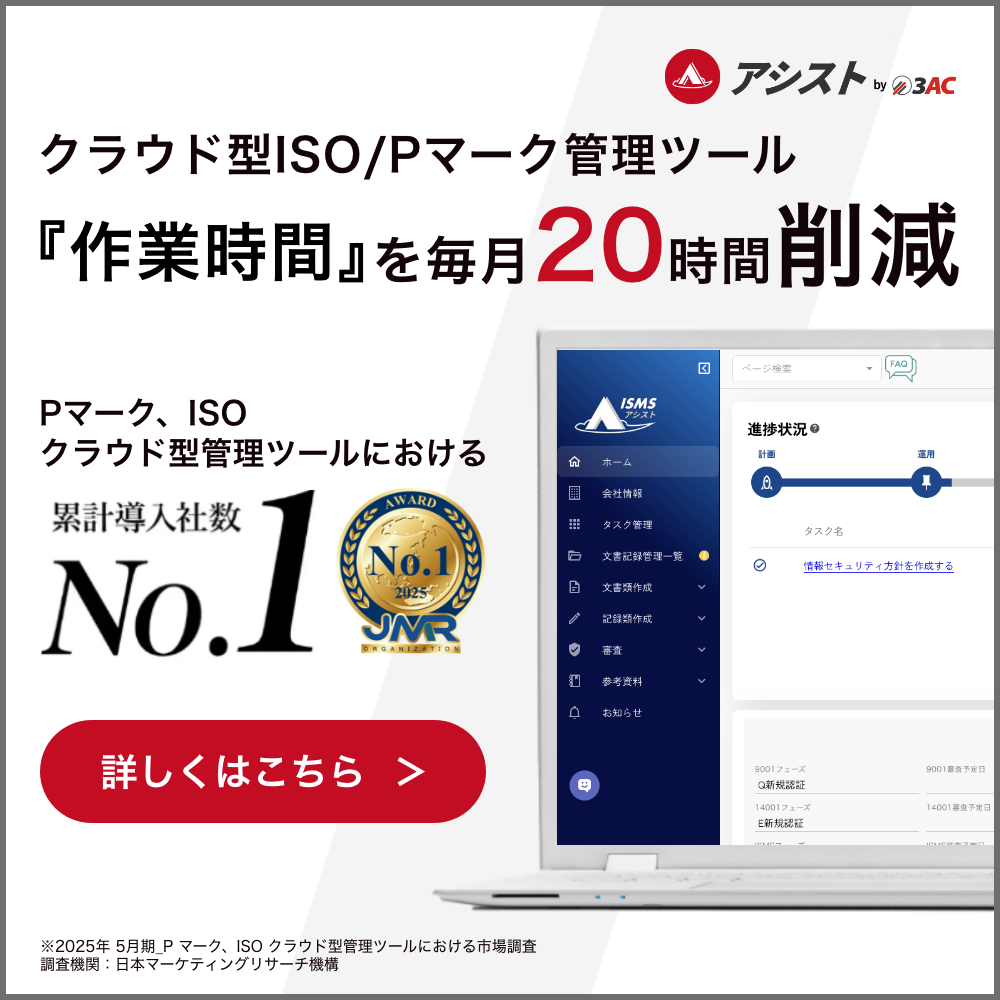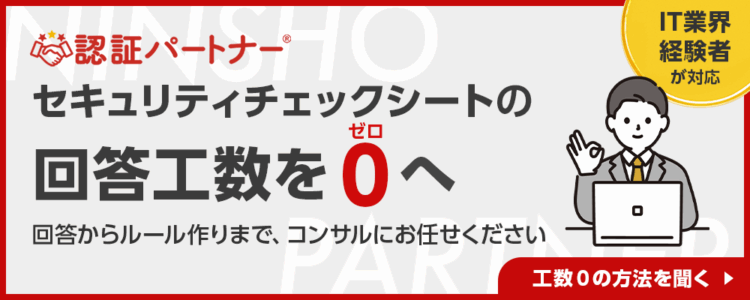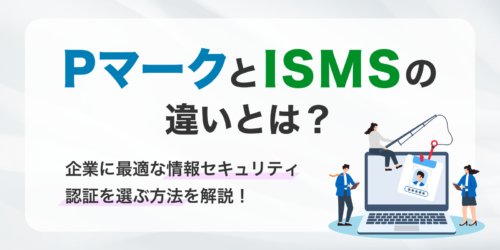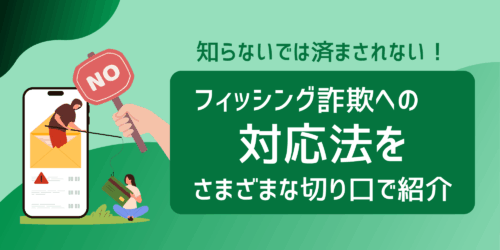2025年5月13日
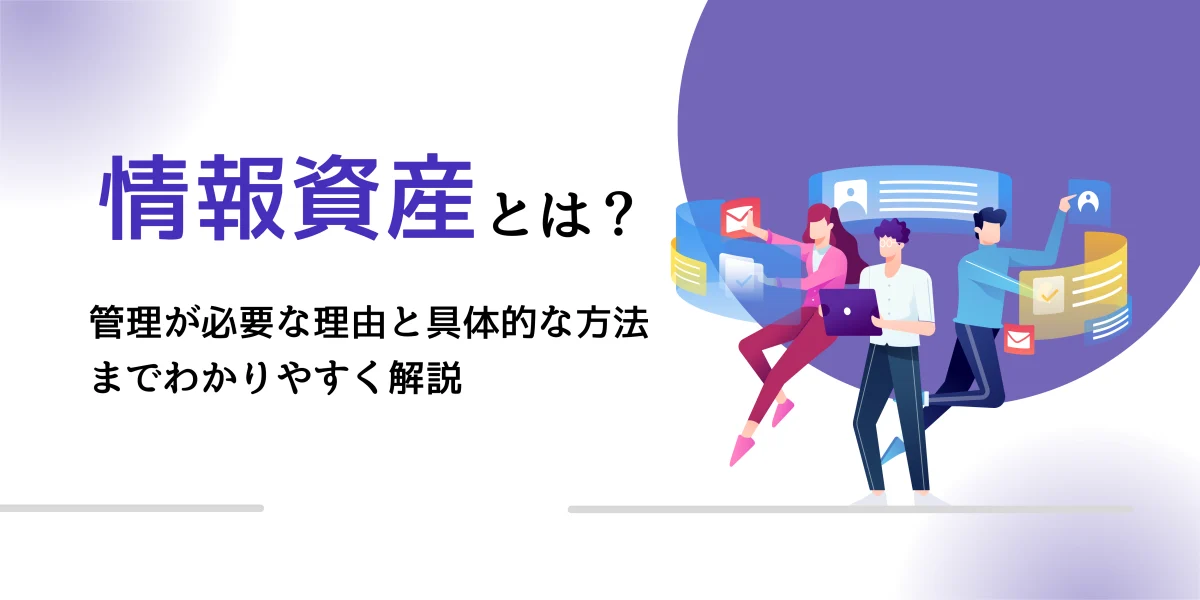
目次
Close
「情報資産って、そもそも何だろう?」
「どうやって管理すればいいのだろうか?」
情報資産とは、「企業や組織が持っている大切な情報と保存しているもの」のことです。
このような情報や媒体などをきちんと管理しないと、情報が外に漏れたり、信用を失ったり、大きなトラブルにつながる恐れがあります。
なぜなら、情報は目に見えない財産であり、正しく守らないと、気づかないうちに大きなリスクに発展してしまうからです。
この記事では、情報資産とは何か、その種類や管理方法、守るためにやるべきポイントまで、わかりやすくまとめています。
最後まで読むことで、情報資産を正しく理解し、今日から自社の大切な情報を守るために何をすればいいかが、しっかりわかるようになります。
1.情報資産とは「企業が持っている大切な情報と保存している媒体」のこと
情報資産とは、企業や組織が持っている大切な情報やそれを記録・保存している媒体を指します。
たとえば、顧客リスト、売上データ、契約書、設計図、メール、パソコン、サーバーなどが情報資産にあたります。
なお、すべての情報が情報資産になるわけではありません。業務の遂行や意思決定、競争力の維持などに寄与するかどうかが、情報資産と見なす際の判断基準になります。
これらの情報資産は、会社の仕事を支える大事な土台です。しっかり管理されていれば、信頼を得たり、ビジネスの強みになったりします。
しかし、情報が外に漏れたり、間違って消えてしまったりすると、大きな損害や信用の失墜につながる危険もあります。
だからこそ、「どんな情報資産があるのか」をきちんと整理し、「どう守るのか」を考えて管理していくことがとても大切です。
日々の業務の中で情報資産を意識し、リスクに備えることが欠かせません。
(1)情報資産の種類
情報資産には、さまざまな種類があります。
たとえば、顧客情報や社員情報といった個人情報、売上データや営業資料などの業務情報、さらには契約書や設計図といった知的財産も重要な情報資産です。
また、これらの情報を保存しているパソコンやサーバーなどの機器も、情報資産に含まれます。
具体的な情報資産の種類は、以下のとおりです。
| 種類 | 具体例 |
| 個人情報 | 顧客リスト、社員名簿、住所、電話番号 |
| 業務情報 | 売上データ、財務情報、営業資料 |
| 法的種類 | 契約書、許認可証、取引先との覚書 |
| 知的財産 | 設計図、企画書、ノウハウ資料 |
| 機器・媒体 | パソコン、サーバー、USBメモリ、外付けハードディスク |
このように情報資産は「情報」そのものだけでなく、それを保存している媒体まで広く含まれます。
それぞれの特徴を理解したうえで、適切に管理することが重要です。
2.情報資産の管理が必要な3つの理由
情報資産の管理が必要とされる理由は、大きく分けて3つあります。
- 経済的な損失を回避するため
- 法令やガイドラインへの違反を防ぐため
- サイバー攻撃に備えるため
もしこのポイントを知らずにいると、大切な情報が漏えいしたり、信用を失ったりするリスクを見落としてしまうかもしれません。
順番に見ていきましょう。
(1)経済的な損失を回避するため
情報資産をきちんと管理することは、経済的な損失を防ぐ上で欠かせません。
なぜなら、情報が漏れたり、データを失ったりすると、賠償金や訴訟費用が発生するだけでなく、企業の社会的信用を失い、売上の減少にもつながるからです。
たとえば、顧客情報の漏えいによって多額の損害賠償を支払ったり、取引先との契約を打ち切られたりするケースも実際に起きています。
また、情報漏えいによってブランドイメージが傷つけば、既存のお客様が離れたり、新しいお客様を獲得できなくなったりするリスクもあります。
実際、東京商工リサーチの調査によると、2024年には上場企業やその子会社で発生した個人情報の漏えい・紛失事故が189件にのぼり、前年より8.0%増加しました。これは2012年の調査開始以来、4年連続で過去最多を更新した記録です。漏えいした個人情報の数は約1,586万人分に達しています。
こうしたリスクを防ぐためにも、自社がどんな情報資産を持っているのかを正しく把握し、漏えいや紛失を防ぐ対策をとることが重要です。
(2)法令やガイドラインへの違反を防ぐため
企業が持つ情報を守るためには、法令やガイドラインをしっかり守ることが大切です。
なぜなら、情報資産を適切に管理できていないと、知らないうちに法律違反になり、行政指導や罰金処分を受けるリスクがあるからです。
たとえば、個人情報保護法に違反した場合、個人情報保護委員会から受ける可能性のある行政処分は以下のとおりです。
- 報告徴収:事案の詳細な報告を求められる
- 立入検査:事業所への立ち入り調査が行われる
- 指導・助言:改善のための指導や助言が提供される 
- 勧告・命令:法令遵守のための具体的な措置が命じられる
参考:個人情報保護委員会「令和5年度個人情報保護委員会 年次報告」
参考:ベリーベスト法律事務所「個人情報漏洩時の罰則は? 漏洩防止対策についても解説」
さらに、個人情報保護法に違反すると、行政からの是正命令や罰金だけでなく、ニュースで大きく報道され、社会的信用を一気に失う恐れがあります。
信用を失えば、取引先から契約を打ち切られたり、売上が急減するなどの深刻な影響が出る可能性もあります。
つまり、自社が保有する情報資産を把握し、法令に則った適切な管理を徹底することは、信用を守り、法律違反を防ぐことにつながるのです。
(3)サイバー攻撃に備えるため
今では、サイバー攻撃は一部の大企業だけの問題ではありません。どの企業でも、重要な情報資産を狙われるリスクを抱えています。
もしサイバー攻撃を受けて情報が漏えいしたり、システムが止まったりすれば、金銭的な損害だけでなく、社会的信用の失墜や事業停止といった深刻な影響を受けかねません。
一度信用を失うと、取引停止や売上の減少に直結することも珍しくありません。また、業務が再開できるまでに長い時間がかかり、企業活動そのものが大きく揺らぐ危険もあります。
2023年、日本国内で確認されたランサムウェア被害は197件に上り、前年から14.3%減少したものの、依然として高水準で推移しています。
被害企業の内訳は、中小企業が57%、大企業が36%、団体等が12%と、企業規模を問わず被害が発生しているとのことです。
また、復旧に1カ月以上かかったケースが20%を超え、被害総額が1,000万円以上となった企業は37%に達しています。
参考:クラウドセキュリティチャンネル「【最新】ランサムウェア国内事例9選!攻撃傾向と対策を解説」
こうした脅威に備えるためにも、自社が保有する情報資産をきちんと把握し、重要なデータには適切なセキュリティ対策を施しておくことが欠かせないのです。
3.情報資産を適切に管理するためにすべき6つのこと
情報資産を適切に管理するには、以下の6つを実施する必要があります。
- 情報資産を洗い出す
- 情報管理台帳を作成する
- 管理方針とルールを決める
- セキュリティ対策を計画・実施する
- 管理を効率化するツールを導入する
- 従業員への教育と意識向上を図る
ひとつずつ解説していきます。
(1)情報資産を洗い出す
まず、「何が情報資産にあたるのか」を正確に洗い出すことが欠かせません。
情報資産と一口にいっても、その種類はさまざまです。
顧客情報、取引先との契約書、財務データ、営業資料、設計図、従業員の個人情報など、企業の活動にとって価値を持つ情報は情報資産に該当します。
一方で、単なる情報は、必ずしも情報資産とは限りません。たとえば、業務とは関係のないニュース記事のコピーや一時的なメモ、会話の中で出た個人的な意見といった情報です。
業務の遂行や意思決定、競争力の維持などに寄与するかどうかが、情報資産と見なす際の判断基準です。
また、これらの情報が保存されているパソコンやサーバー、USBメモリなどの機器も、情報資産として管理すべき対象となります。
洗い出し作業を行う際は、各部門ごとにどのような情報を扱っているかを丁寧に確認し、リストアップしていくことが大切です。
このとき、情報の種類だけでなく、保存場所やアクセス権限についても把握しておくと、後の管理方針の策定がスムーズに行えます。
(2)情報管理台帳を作成する
情報資産を洗い出した後は、それらの情報を整理する必要があります。
そのときに役立つのが、情報資産管理台帳です。
情報資産管理台帳とは、会社が保有している情報をまとめて記録した一覧表のことです。
具体的には、情報の名前、保存場所、管理している担当者、情報の重要度などを整理して書き出します。
情報資産管理台帳を作成することで、企業の活動に対して価値を持つ情報かどうかを区別し、どこを重点的に守るべきかが明確になります。
たとえば、顧客情報や設計図のような重要な情報は、厳しくアクセス管理をする必要がありますし、業務メモなど重要度が低い情報には、そこまで厳格な管理は必要ありません。
このように、情報の重要度に応じた適切な管理を行うためにも、情報資産管理台帳の作成を行いましょう。
(3)管理方針とルールを決める
次に、「どのように管理するか」という方針とルールを定めましょう。
ここでいう管理方針とは、たとえば、
- 情報資産は社内だけで使用し、外部への持ち出しを禁止する
- 個人情報は一定期間保管後、適切に削除する
といった基本的な考え方を指します。
そしてルールとは、その方針に基づき、
- 重要なデータにはパスワード設定を必須とする
- USBメモリなどの使用を制限する
- 退職者のアカウントは即日削除する
など、具体的な行動基準を定めることです。
管理方針とルールをしっかり決めることで、従業員一人ひとりが何を守るべきかを正しく理解し、日々の業務に反映できるようになります。
これらは、定期的に見直しを行い、現場に合わせた実効性のあるルールを維持していくことも大切です。
(4)セキュリティ対策を計画・実施する
情報資産を守るためには、事前にセキュリティ対策を計画し、確実に実施していくことが大切です。
行き当たりばったりの対応では、リスクを十分に防ぐことはできません。
まずは、自社が抱えるリスクを洗い出し、優先順位をつけて対策計画を立てましょう。
たとえば、重要な情報資産への対策を最優先にし、各対策について具体的な期限と担当者を設定します。
また、計画には定期的な点検や見直しのスケジュールも組み込み、状況の変化に応じて柔軟に対応できる体制を整えることも重要です。
とくに、サイバー攻撃の手口は日々変化しているため、計画も一度立てたら終わりではありません。継続的に見直しを重ね、常に最新のセキュリティ水準を保つことが求められます。
(5)管理を効率化するツールを導入する
情報資産の管理には、専用のツールを導入して、業務の効率化を図ることが重要です。
手作業だけで情報資産を管理しようとすると、どうしても抜け漏れや更新忘れが発生しやすくなります。また、管理する対象が増えるほど作業量も膨大になり、負担が大きくなってしまいます。
たとえば、情報資産を一覧で管理できるシステムを導入すれば、資産の登録、更新、棚卸し作業を一元化でき、抜け漏れやミスを防ぐことができます。代表的なものには、Sky株式会社の「SKYSEA Client View」などがあげられます。
情報管理ツールを導入することで、担当者の負担も大きく軽減でき、正確で一貫性のある情報資産管理が可能です。
限られたリソースの中で、情報資産を確実に管理していくためにも、ツールの導入を検討することをおすすめします。
(6)従業員への教育と意識向上を図る
システムや仕組みだけでなく、従業員一人ひとりの意識を高めることも忘れてはいけません。
どれほど技術的な対策を整えても、現場での意識が低ければ、思わぬミスやルール違反によって情報漏えいが発生する恐れがあります。
そのため、まずは情報資産の重要性や、正しい取り扱い方法について、定期的に教育を行うことが大切です。
たとえば、パスワードの管理方法、社外への情報持ち出しの禁止、不要になった情報の適切な廃棄方法など、日々の業務に直結する内容をわかりやすく伝えると、実践につながりやすくなります。
教育後には理解度を確認するテストを実施したり、現場でルールが守られているか定期的にチェックする仕組みを取り入れると、より意識の定着に効果があります。
また、教育は一度きりで終わらせず、年に数回、意識を振り返る機会を設けることも重要です。従業員全体の意識が高まることで、組織全体の情報資産管理レベルも向上していくはずです。
4.情報資産を管理する際に押さえておくべき施策2選
情報資産は一度、チェックをすれば終わりではありません。管理された状態を維持・改善していくことも重要です。具体的には、以下の2つです。
- 内部監査を実施する
- 外部のリスク評価を活用する
順番に紹介していきます。
(1)内部監査を実施する
情報資産を適切に管理・維持するためには、定期的に内部監査を実施することが大切です。
管理体制を整えたとしても、時間が経つにつれて運用のずれやルール違反が起きることは避けられません。
内部監査を行うことで、こうした問題を早い段階で発見し、適切に修正することができます。さらに、現場を第三者的な視点で見直すことで、管理体制の弱点や見落としにも気づきやすくなります。
たとえば、情報資産管理台帳が最新の状態になっているかを確認し、未更新の部分があれば、すぐに更新ルールを徹底します。アクセス権限に不備が見つかった場合は、設定フローを見直し、適切に再設定します。
また、重要情報の廃棄ルールが守られていない場合には、従業員への再教育や必要に応じたルールの見直しも検討しましょう。
内部監査は単なるチェックにとどまらず、発見した問題を確実に是正するための重要な取り組みなのです。
(2)外部のリスク評価を活用する
情報資産の管理には、自社だけで管理体制を評価するのではなく、外部のリスク評価を積極的に活用することも重要です。
自社内部だけで点検を行っていると、どうしても視点が偏ったり、リスクを見落としたりする可能性があります。
外部の専門機関によるリスク評価を受けることで、客観的な立場から管理体制の強みや弱点を洗い出し、より高い精度での改善策を検討できるようになります。
たとえば、外部の監査機関によるセキュリティ診断では、
- 情報漏えい発生時の初動対応手順が整備されていない
- バックアップ体制が不十分で、障害発生時にデータを復旧できない
- 委託先の情報管理が甘く、間接的な漏えいリスクを抱えている
など、内部では見落としがちなリスクを具体的に指摘されることがあります。
外部の専門機関の評価結果をもとに、必要な対策を講じることで、より強固な管理体制を築いていくことができるはずです。
5.まとめ
今回は、情報資産管理における基本的な意味から種類、情報資産の適切な管理方法について、解説しました。
情報資産とは、会社や組織が保有する大切な情報や保存しているものを指します。
これらの情報を適切に守らなければ、情報漏えいや改ざん、なりすましなどのリスクが発生し、信用失墜や業務停止といった深刻な影響を受ける恐れがあります。
情報資産を守るためには、内部・外部からの適切な対策が重要になります。
「わが社の情報資産は、本当に安全に管理できているだろうか?」
「見えないリスクに気づかず、重大な問題を引き起こしてしまわないだろうか?」
そうした不安をお持ちの方は、ぜひ認証パートナーにご相談ください。
専門スタッフが無料相談を通じて、貴社の情報資産の管理状況に合わせた最適な対策をご提案いたします。
ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!
認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。
経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。
▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間
- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間
- 審査資料の準備:20時間→0.5時間
認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。
ISO・Pマーク(プライバシーマーク)の認証・更新も安心
認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!
信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!
一目でわかる
認証パートナーのサービスご説明資料
8,000社以上の支援実績に裏付けされた、
当社サービスの概要を紹介しております。
資料の内容
- ・一目でわかる『費用』
- ・一目でわかる『取得スケジュール』
- ・一目でわかる『サポート内容』
ISMS(ISO27001)認証パートナー
サービスのご案内
認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。
お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。
-
Pマーク
個人情報保護マネジメントシステム
高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。
認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -
ISO9001
品質マネジメントシステム
品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。
認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -
ISMS・ISO27001
情報セキュリティマネジメントシステム
情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。
認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -
ISO14001
環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。
認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -
ISO27017など各種対応規格
ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。
ISO27017など各種対応規格ページへ -
複数規格の同時取得
ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください
複数規格の同時取得ページへ
- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.